考えることは良いことだ。しかし、残念ながら、それでは生活費を払えない。
極端な選択をするか、もともと余裕があるかでなければ、このルールからは逃れられない。「生きるためにお金が必要」であり、「考えるためには生きる必要がある」。
逆は必ずしも真ではない。しかし、人間が「考えることができる」からこそ、生活水準が時代とともに(基本的には良い方向へ)進化してきたのではないだろうか?
しかし、一つ変わっていないものがある。それは、「大衆」の思考との向き合い方だ。
システムは巧妙に設計されており、大衆が考えなくても済むようになっている。これは彼らの「せい」ではない。社会そのものがそういう仕組みになっているのだ。
仕事を頑張り、子どもや家族の世話をし、2~3人の友人となんとか連絡を取り合い、たまに夜や週末に(残業しすぎた時には)少し楽しむ。
こうして日々を過ごしていると、人生の根本的な問いについて考える時間もなければ、多くの人にとっては「考えたい」という気持ちすら湧かない。
「娯楽」を求めるとき、哲学や勉強が自然に選ばれることはほとんどない。そもそも、なぜ「娯楽」が必要なのか?
多くの人にとって、それは時間を潰すため、退屈を埋めるため、考えなくて済むようにするため。
なぜなら、考えることはしばしば「痛み」を伴うから。
自分がもっと良くできたはずだと気づくこと。過去に失敗したことを理解すること。そして、これから起こるかもしれない(あるいは起こらないかもしれない)ことに不安を感じること。
そして、それがまた繰り返される。
「Alors on danse(さあ、踊ろう)」—ある歌詞のように。
お酒を飲み、好きでもない仕事や満たされない人間関係に文句を言いながら。
政治家の無能さを笑い、まるで自分ならもっと上手くやれるかのように語り合う。
一人でカウンターに座る人を見て、「友達がいない」と笑う。
飲みすぎて吐いてしまった人を見て笑う。
そして、すでに夜は更け、翌朝には仕事がある。
寝不足で頭がぼんやりしたまま、スマホをスクロールして目を覚ます。考えさせられるような投稿はスルーする—面倒だから。
時間を気にせずダラダラしていたら、仕事に遅刻しそうになる。
好きでもない仕事だが、お金を稼ぐためには仕方がない—「戦争の要」だから。
ついでに、モチベーション系の投稿をいくつか目にする。「ポジティブになれ」「運動しろ」「瞑想しろ」。
どれも真実ではあるが、それらが機能するためには、まず自分で深く考える時間が必要。しかし、その時間を取っていない。
そこで思ったのだが、もしも場所や企業、商品、映画、本、マンガ、音楽、あらゆるものに「意識レベル」を示すラベルがついていたらどうだろう?
私の理論では、「脳に良いもの=意識の向上に役立つ」。これは一部の商品については明らかだ。
例えば、今日は『シンドラーのリスト』についての投稿を書いた。
映画は娯楽だ。しかし、ホロコーストを扱った映画は、90年代のアクション映画とは違う(まあ、ここで議論する人もいるだろうが…例え話だ)。
『シンドラーのリスト』には、アクション映画よりも「意識ポイント」が多くつくだろう。
アプリも同じ。
ガチャゲームは中毒性を生み、脳にとって極めて悪影響—マイナスポイント。
広告なしで健康を促進するアプリ—プラスポイント。
政府がこうした「スコア」と連携するべきだが、汚職やロビー活動なしで。それが「政府」では矛盾しているというのがまた皮肉だが。
ともあれ、もう時間がない。書いても飯は食えない。まだ?
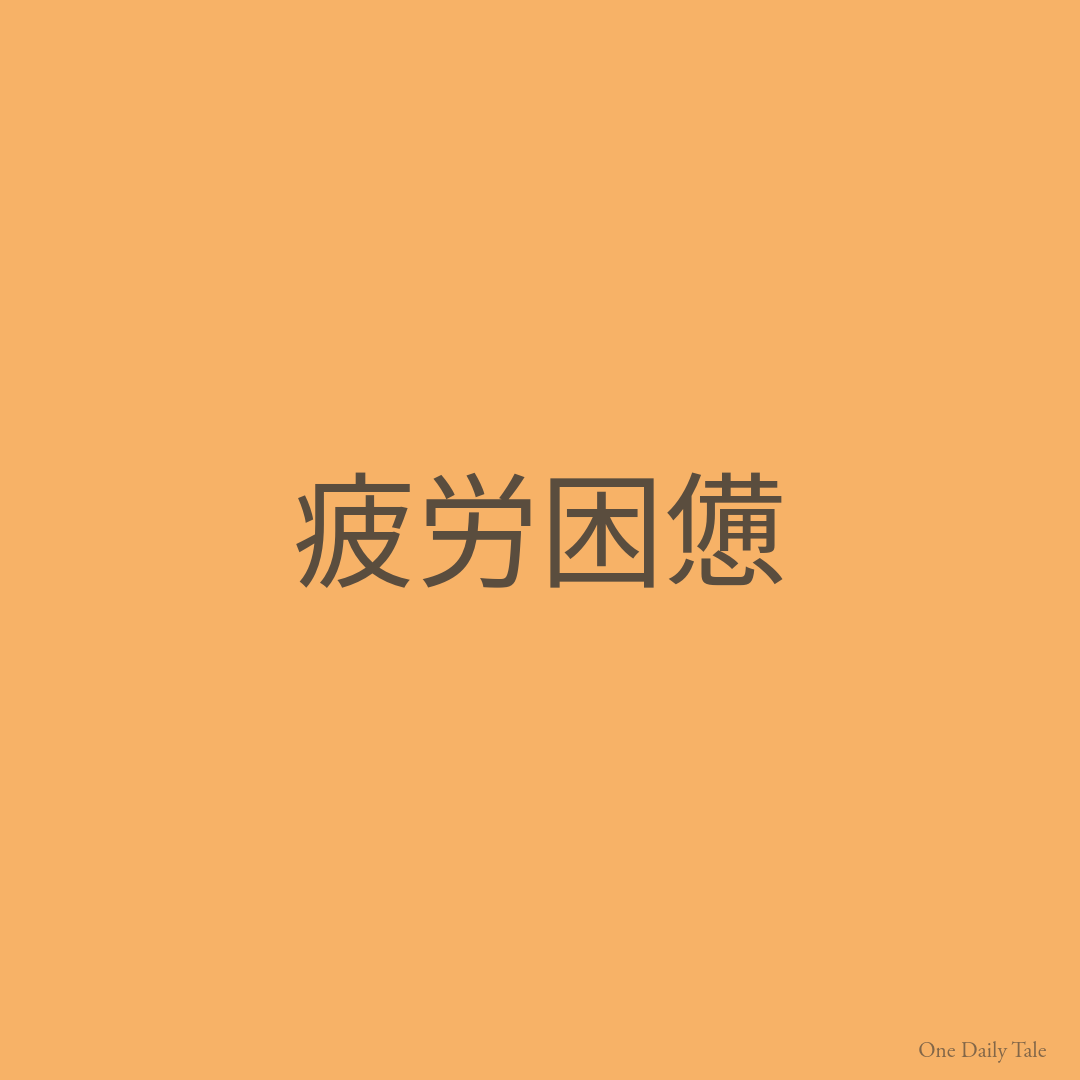
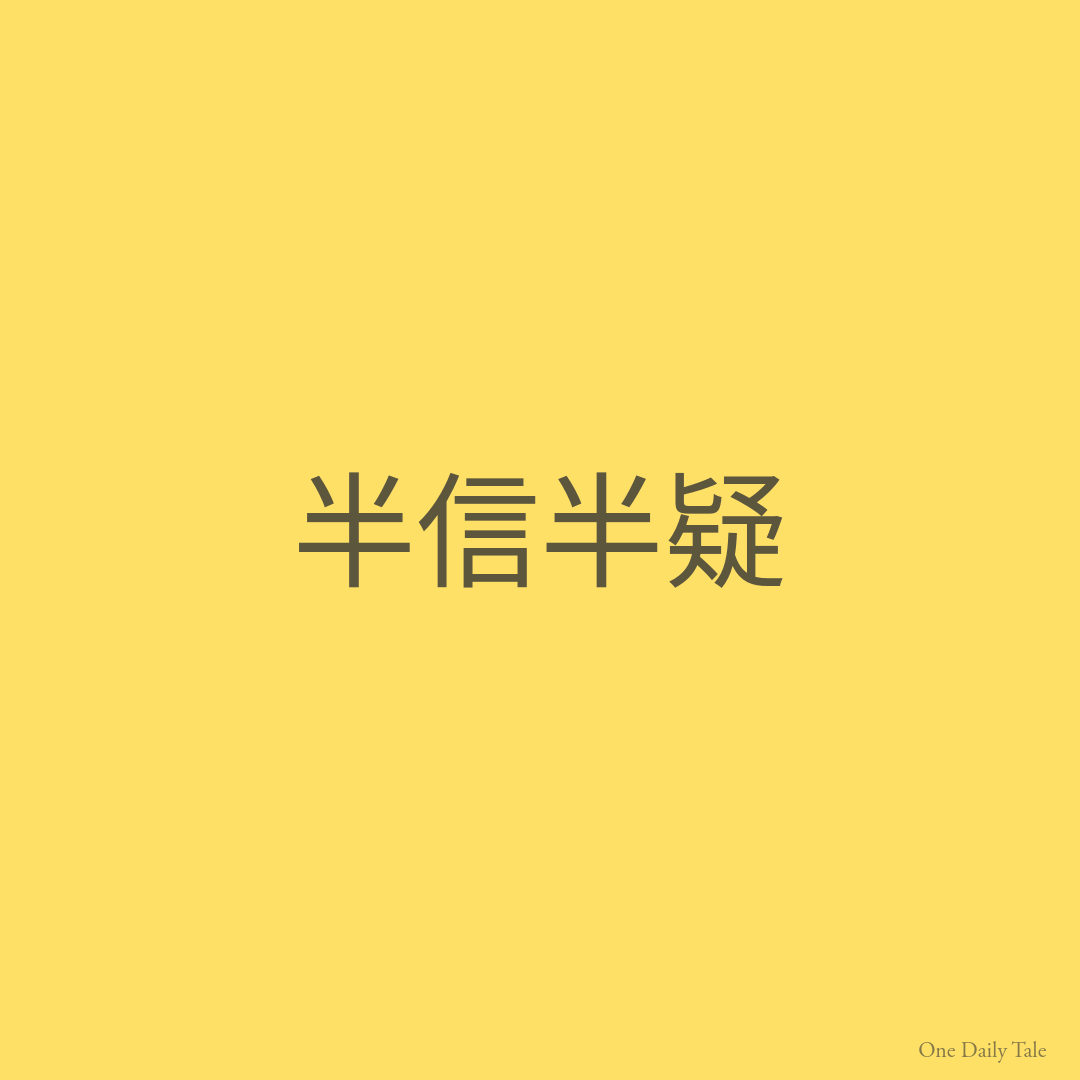
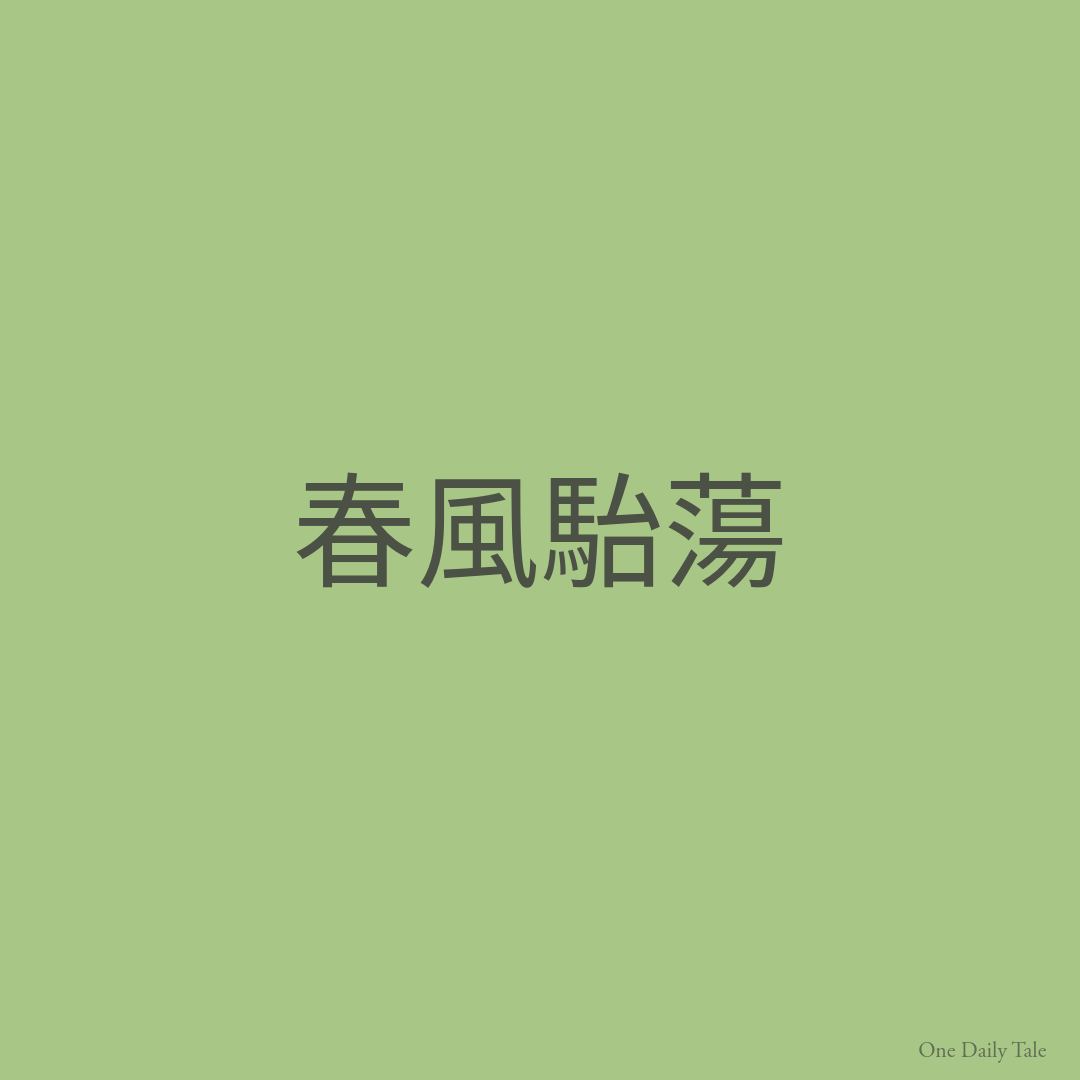
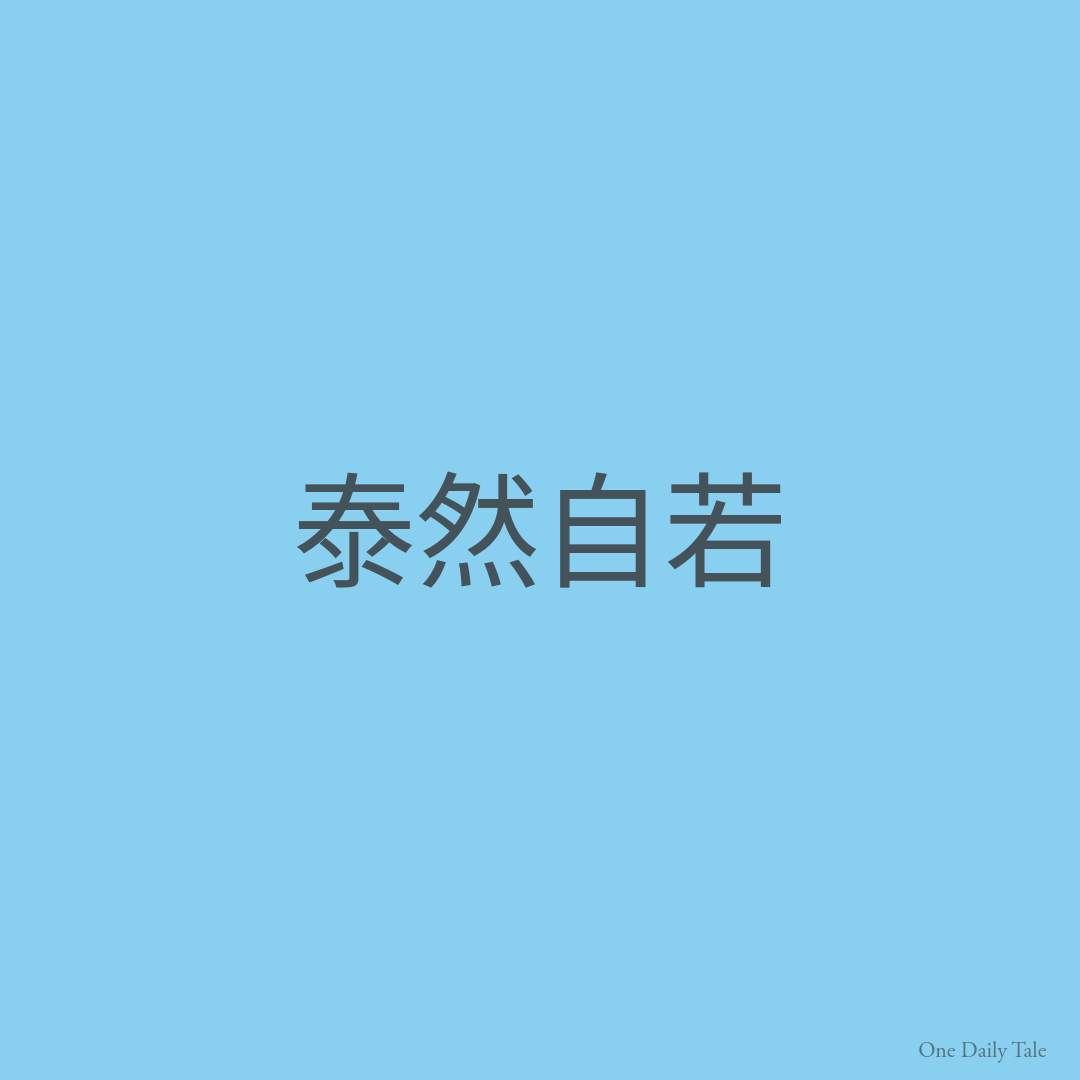
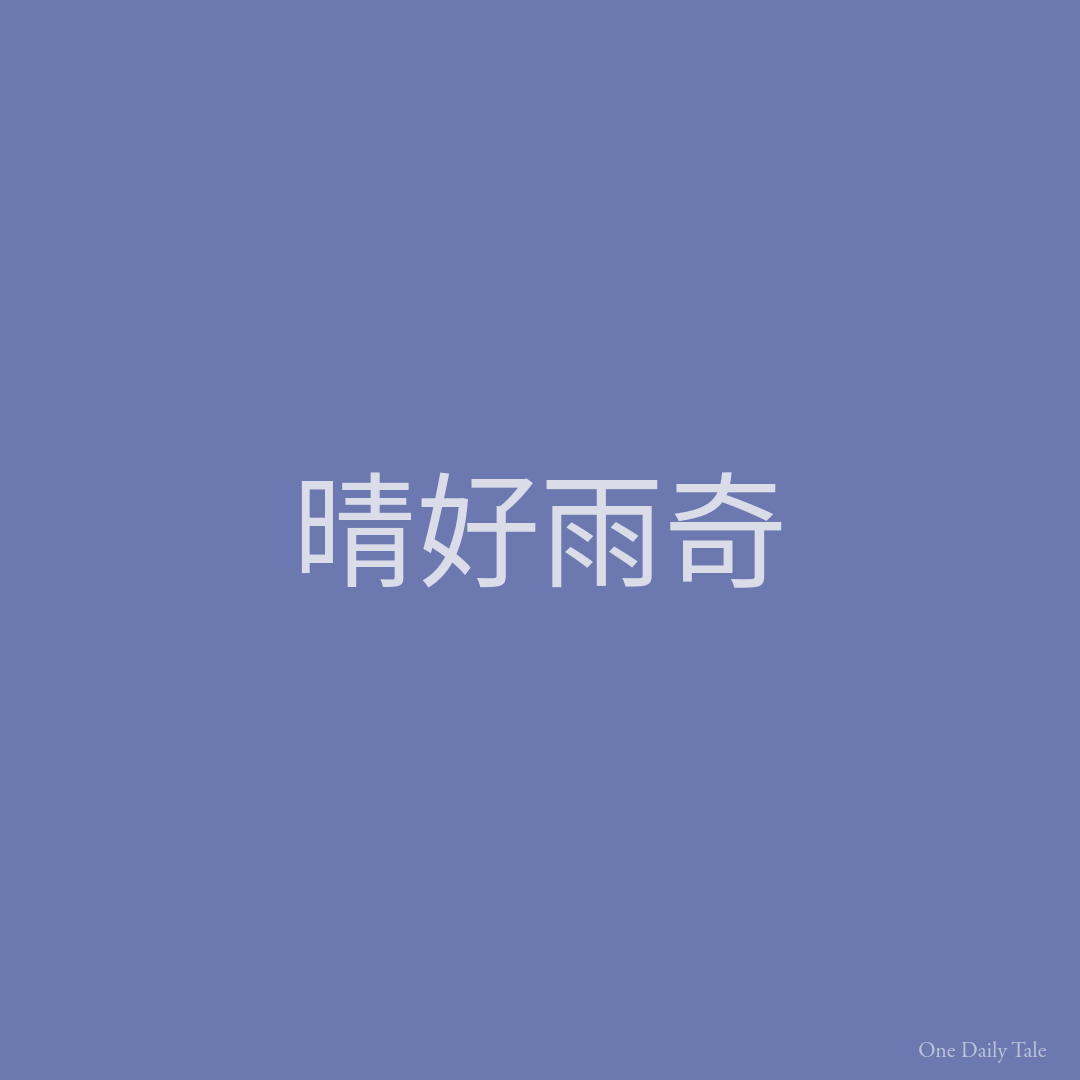
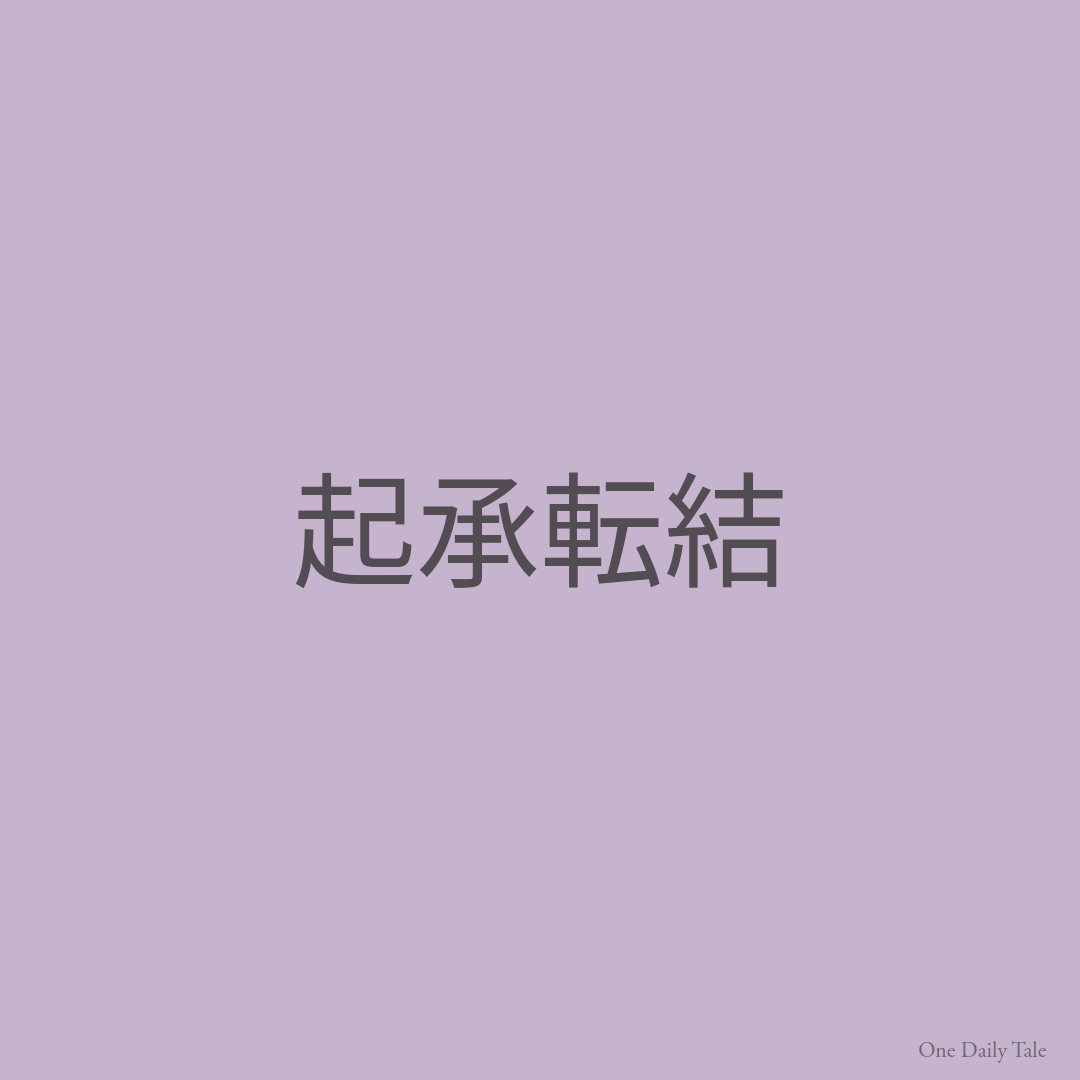
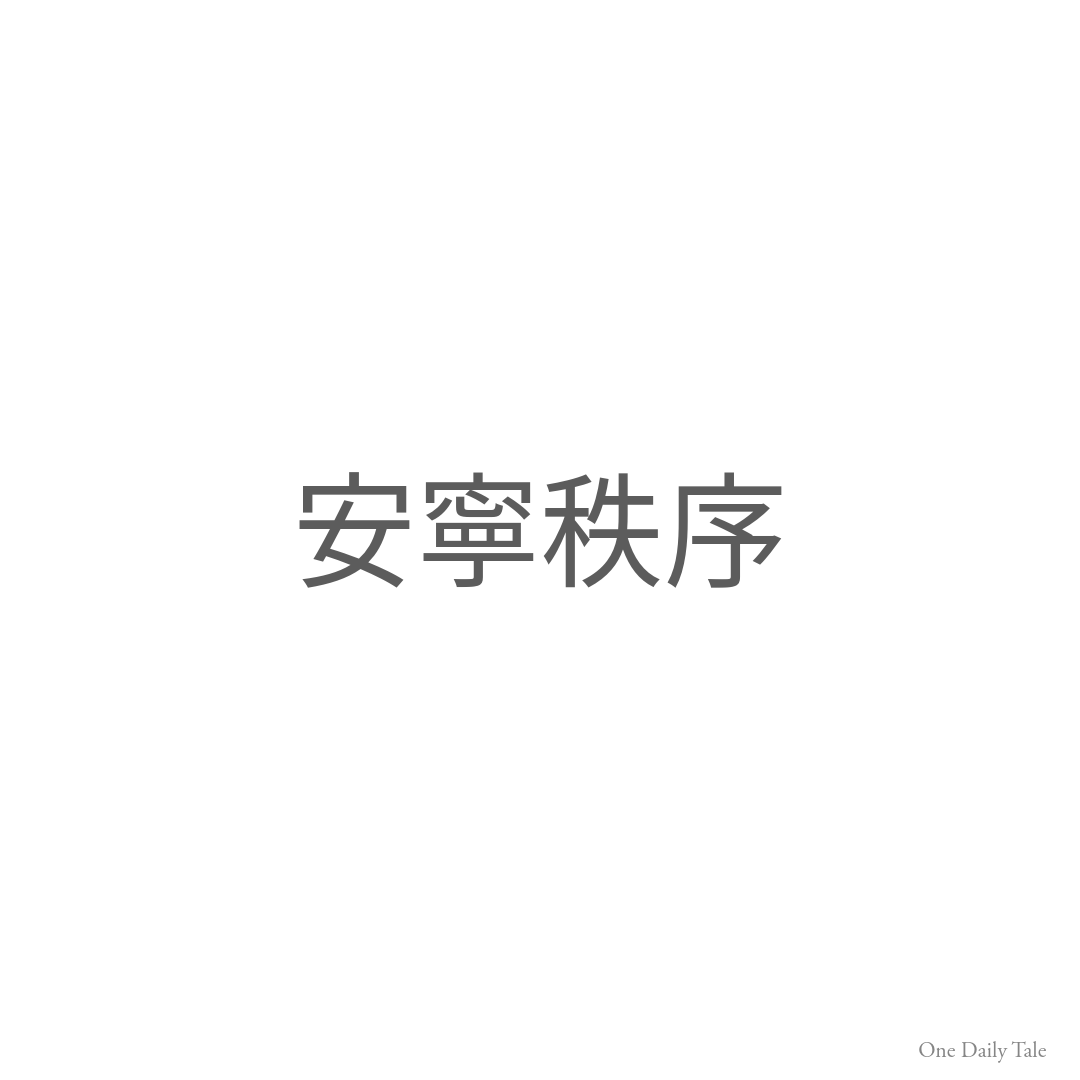
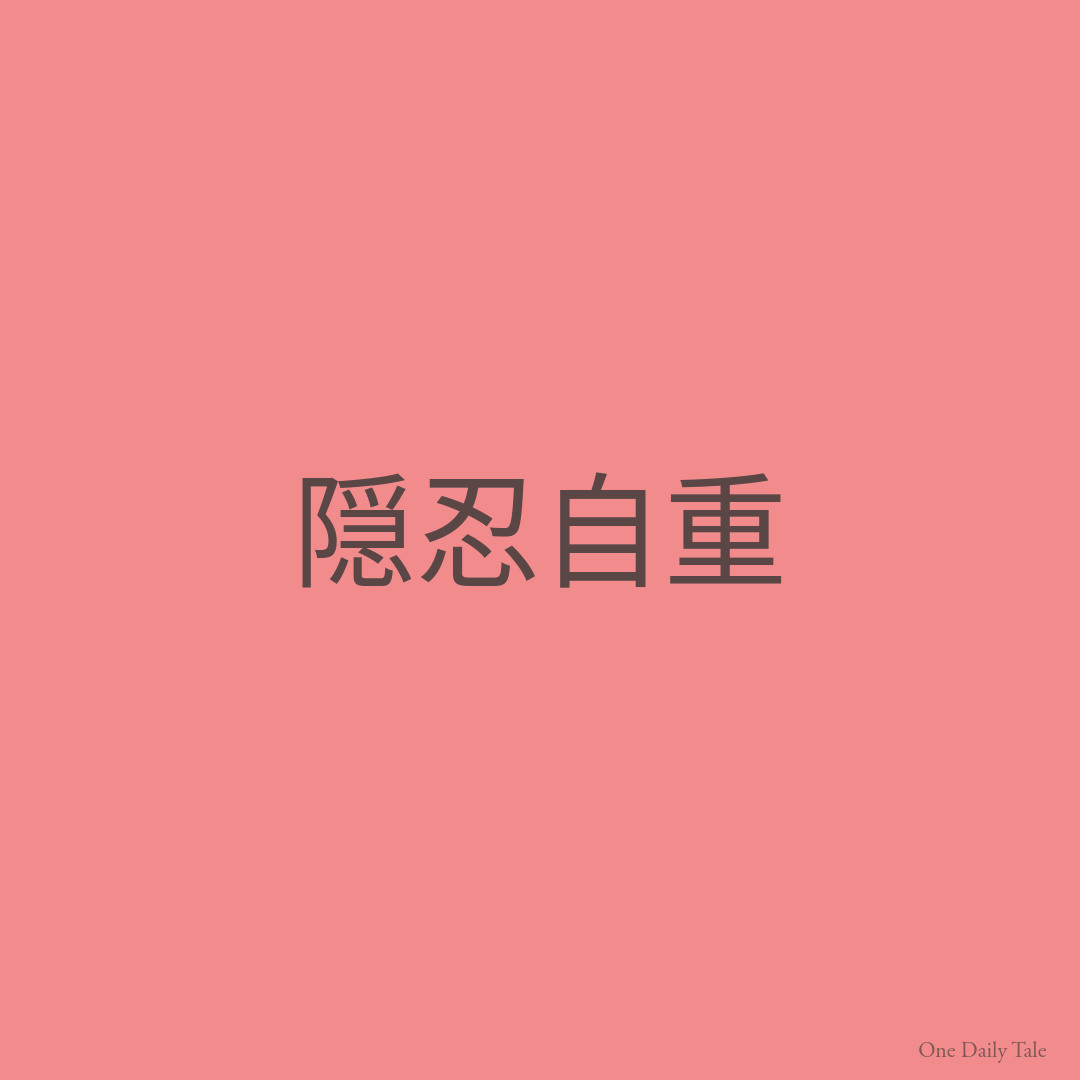
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。