

最新の投稿
-
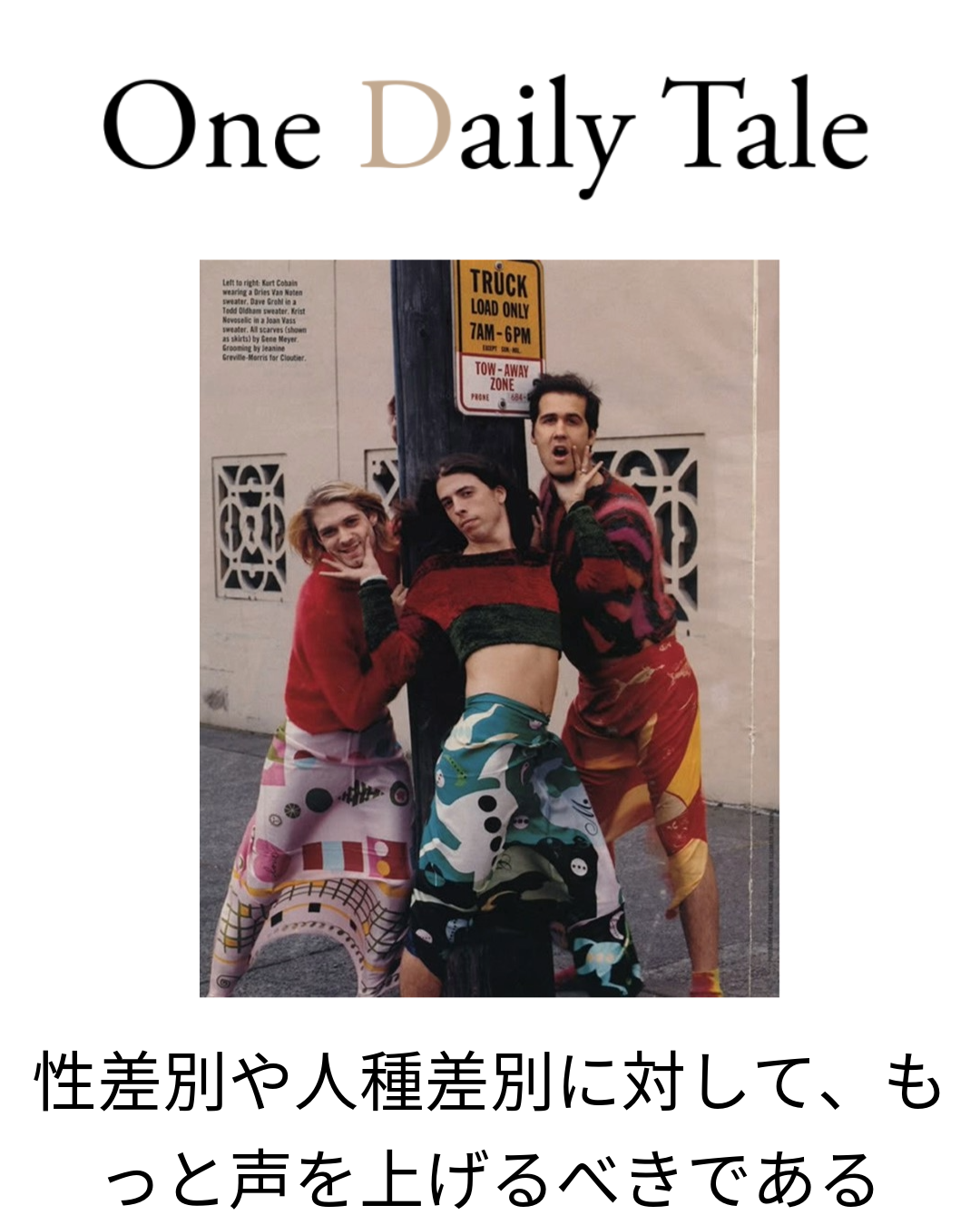
-
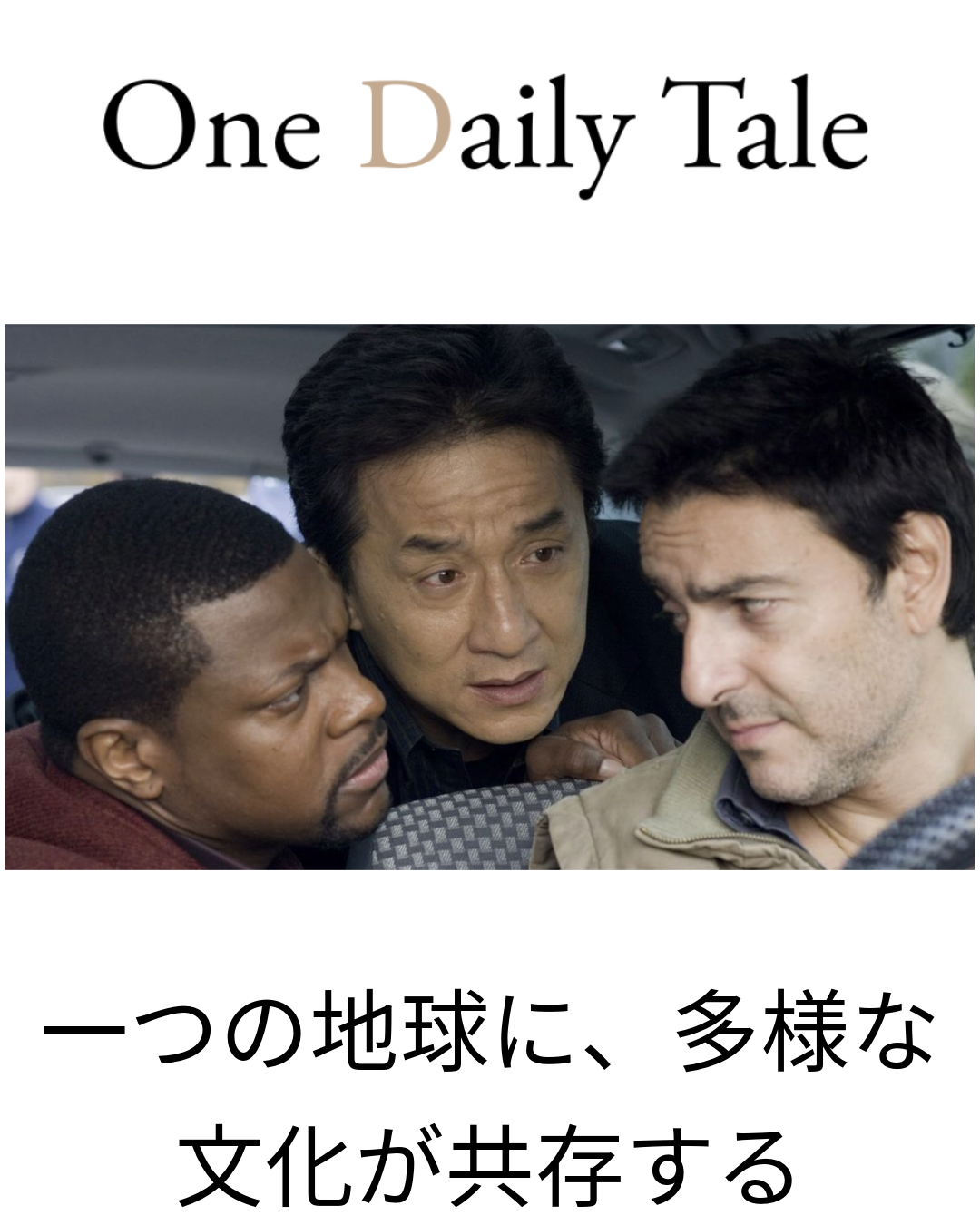
『ラッシュアワー』シリーズはいかに偏見を打ち破り、団結を促すか
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について
-

-

ブレス オブ ファイアII:この名作が「偽りの敵を作る」のではなく「違いを受け入れる」ことを教えてくれる理由とは?
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について
-

『La Haine(憎しみ)』:極端な視点は問題の本質を解決する方法ではない
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について
-

テルマエ・ロマエ:異なる文化を混ぜることで新たなアイデアが生まれる
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について
-
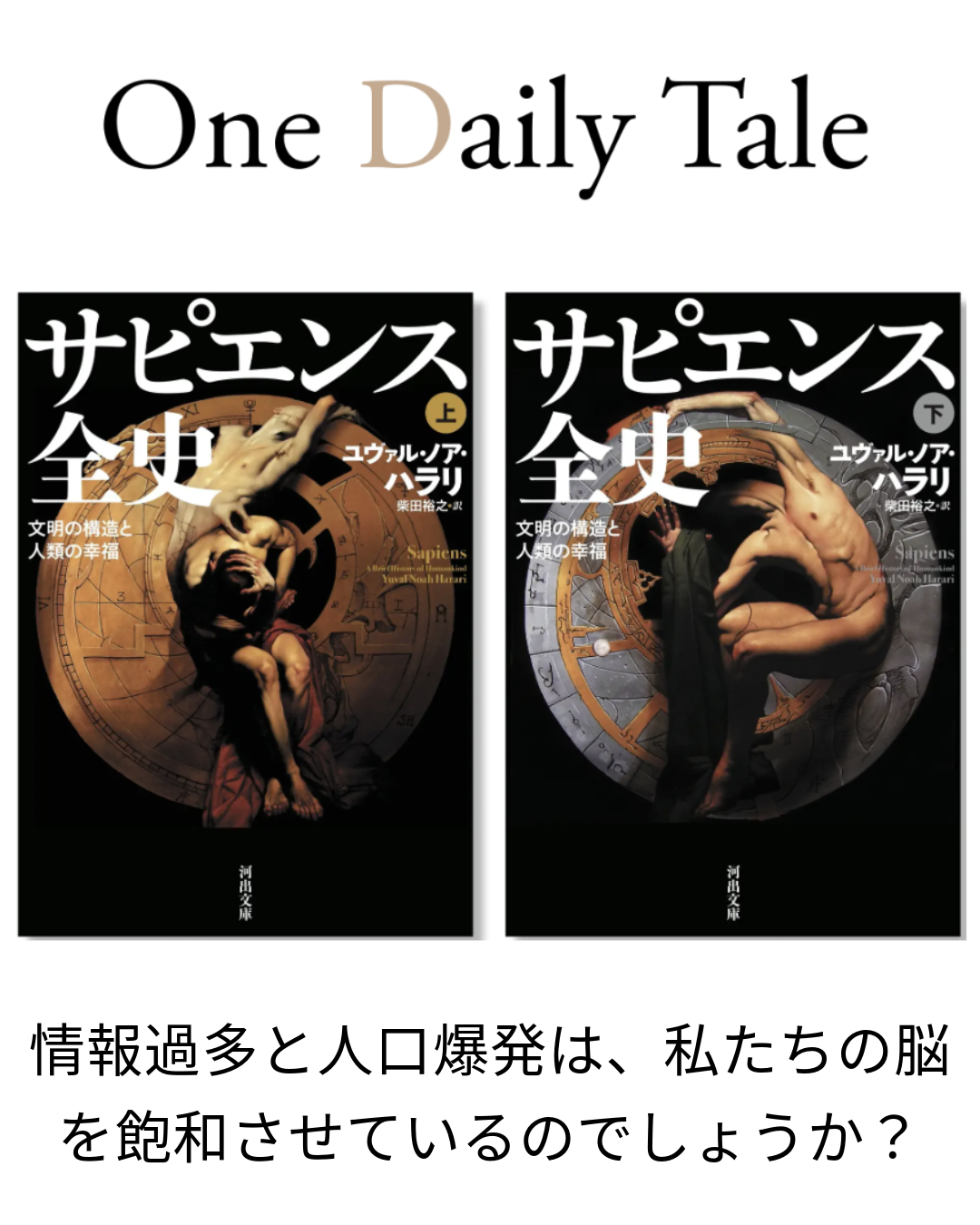
-
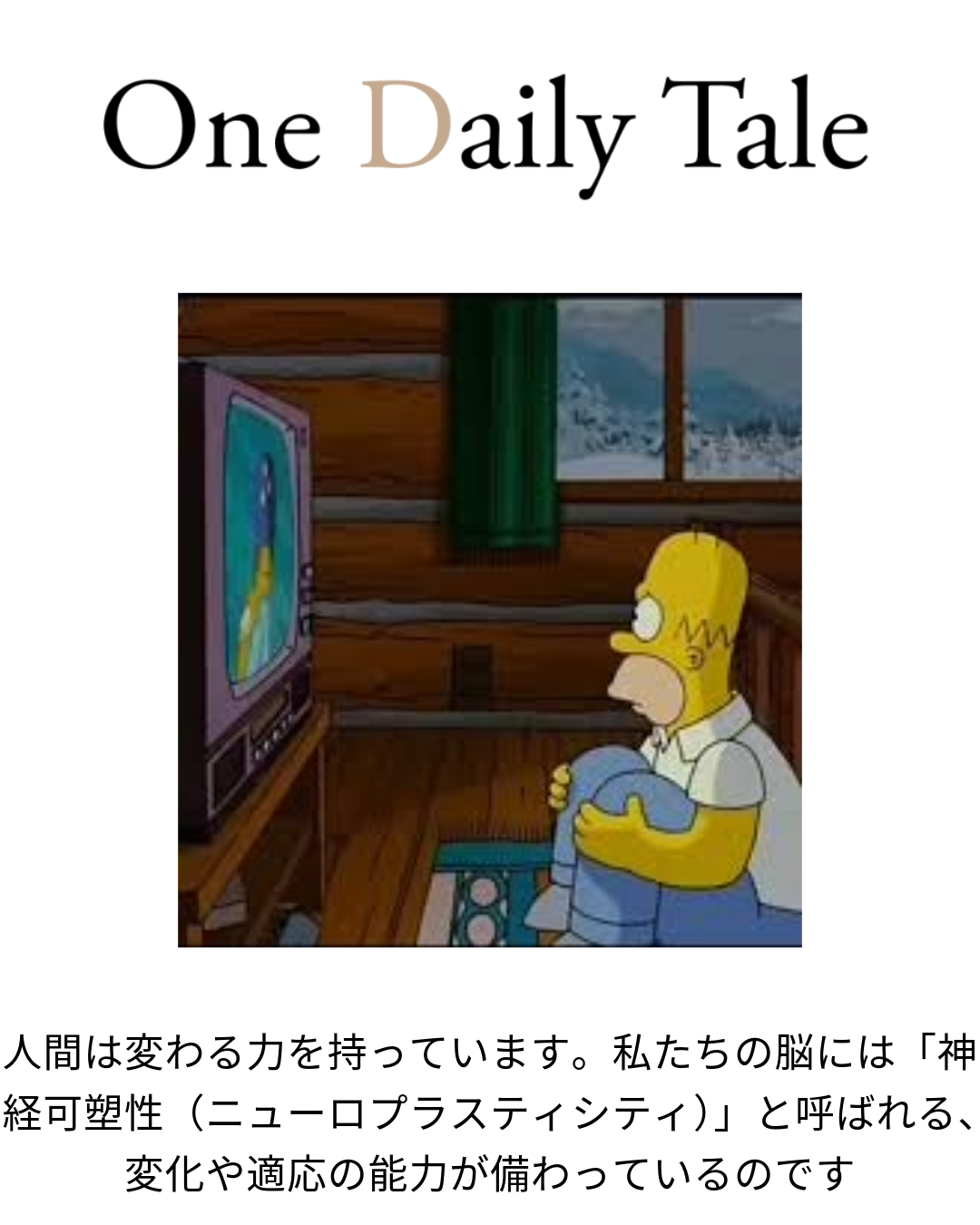
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。