最近、クライミングについての記事を書いていて、今日ゲームについて考えていたところ、「メタルギアソリッド3 スネークイーター」の象徴的なはしごのシーンを思い出しました。この忘れられない場面では、おそらくゲーム史上最長のはしごの登攀が描かれています。このシーン中、美しい曲が流れ始め、単なる登攀が心に残る物語へと昇華します。
小島秀夫が監督を務めた2004年発売のメタルギアソリッド3 スネークイーターは、シリーズ5作目であり、メタルギアシリーズ全体の前日譚として位置付けられています。本作では、プレイヤーはネイキッド・スネーク(声:大塚明夫/デビッド・ヘイター)を操作し、後の伝説的なビッグ・ボスとなる彼の物語を追体験します。1998年のメタルギアソリッド以来、このシリーズはインタラクティブな映画とゲームの境界を曖昧にすることで高く評価されています。ジェームズ・ボンドのようなスパイ映画からの影響を受け、主人公は1981年公開の映画ニューヨーク1997のスネーク・プリスケンに部分的にインスパイアされています。
登攀が象徴するもの
はしごを登ることは日常生活ではありふれたことに思えるかもしれませんが、このシーンでは深い象徴性を帯びています。2分以上にわたる安全措置なしの登攀は、頂上にたどり着かなければならない緊張感を伴うフリーソロを彷彿とさせます。このシンプルで緊張感のあるシーンは、流れる曲によって象徴的な旅へと変貌します。
人間の脳は本能的に物語に引きつけられる性質があります。サピエンス全史やAIについての新刊ネクサス(まだ読んでいません!)の著者、ユヴァル・ノア・ハラリは、事実だけでなく魅力的な物語を語ることができる人が、世界により大きな影響を与えると述べています。映画やゲームが登場する以前、物語は口伝えで伝えられ、教訓や危険への警告として機能しました。この物語への生来の結びつきは、はしごの登攀のようなシンプルな要素にも意味を見出させます。
ドーパミンとの関連性
このシーンはまた、ドーパミンが私たちの行動にどのように影響を与えるかを暗示しています。脳のドーパミンシステムは、快楽や動機付けを生み出し、刺激の種類に関係なく同じように機能します。チョコレートを食べること、ゲームに夢中になること、ソーシャルメディアをスクロールすることなど、すべて同じシステムが作動しています。
近年、このシステムは強迫的行動における役割が注目されています。ドーパミンの刺激自体は有害ではありませんが、過剰に刺激されると依存に似た傾向を引き起こす可能性があります。ドーパミンとその影響に関する教育が普及すべきであり、多くの強迫的行動は理解の欠如から生じています。一度依存が形成されると、それから脱却するのは非常に困難であり、強い意志とサポートが必要です。
リアリズムの教訓
メタルギアソリッド3のユニークな特徴の一つは、通常のライフバーに加えて、スタミナバーや怪我の管理がある点です。プレイヤーはスタミナを維持するために食べたり、怪我を治療したりする必要があります。ゲームにリアリズムを加えることが常に必要とは限りませんが、それは現実生活との重要な類似点を強調します。
One Daily Taleでは、日々の習慣が社会を形作ると強調しています。ゲームと同様に、良い栄養、質の高い睡眠、健康的な生活は、私たちが繁栄するための基盤です。これらが欠けてしまうとエネルギーが減少し、日常生活の要求に応えるのが困難になります。この物語性とリアリズムの組み合わせは、ゲームでも現実でもバランスの重要性を思い出させてくれます。
あなたの考えを聞かせてください
メタルギアソリッド3のようなゲームが、物語性やリアリズムを通じてどのように強い印象を与えるかについて、あなたはどう思いますか?これらの要素は、私たちの日常生活や習慣の見方に影響を与えることができるでしょうか?ぜひコメントでお聞かせください!
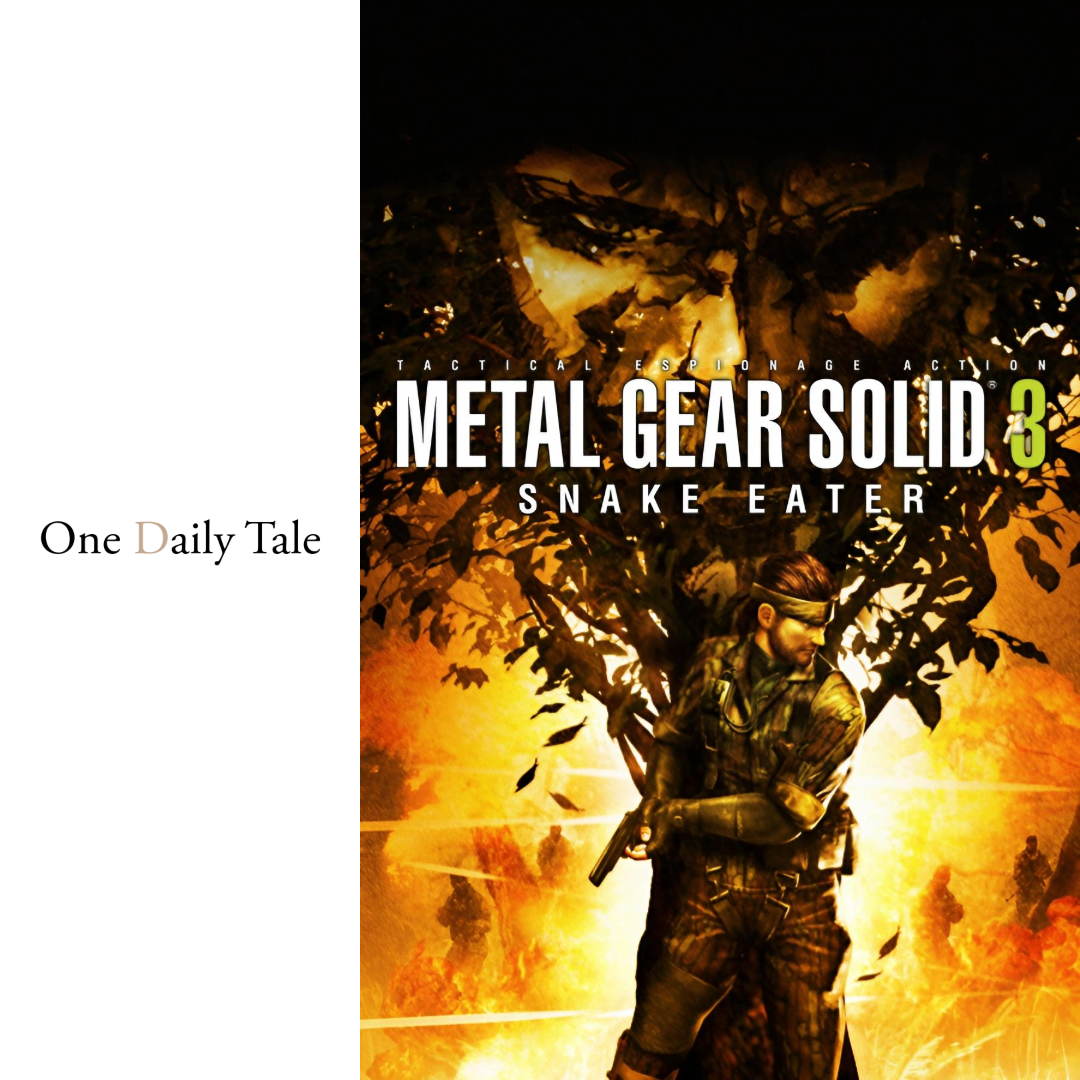
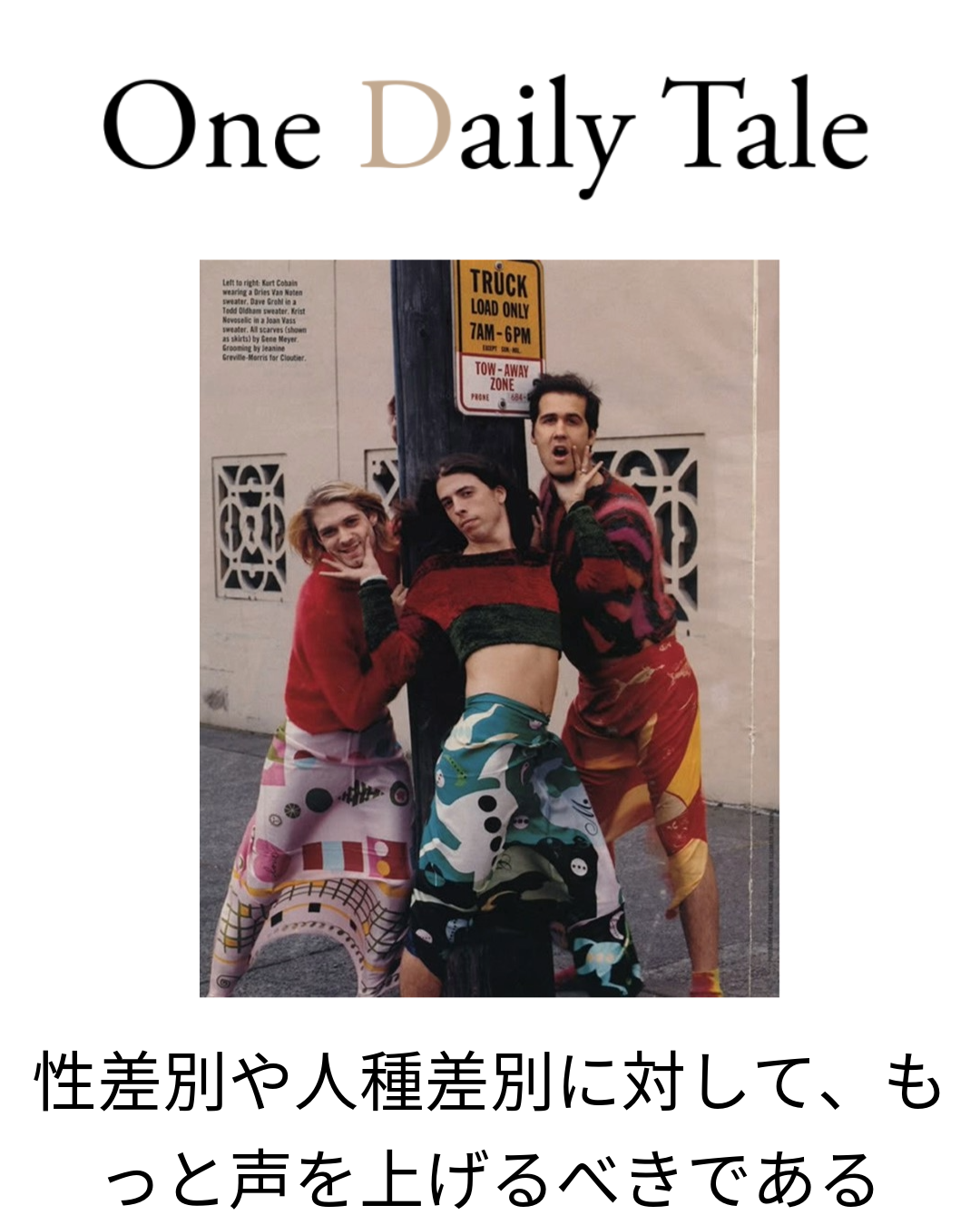
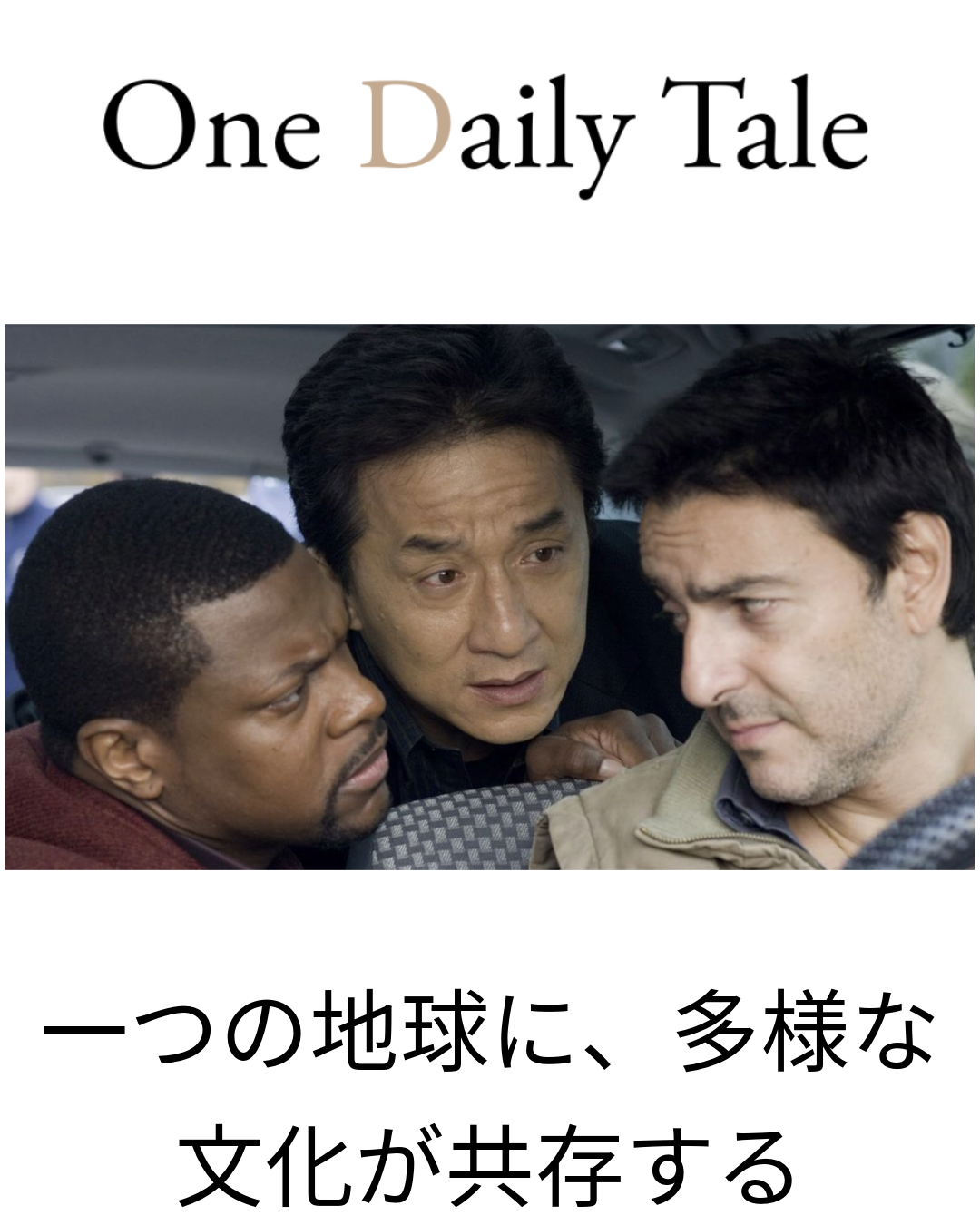




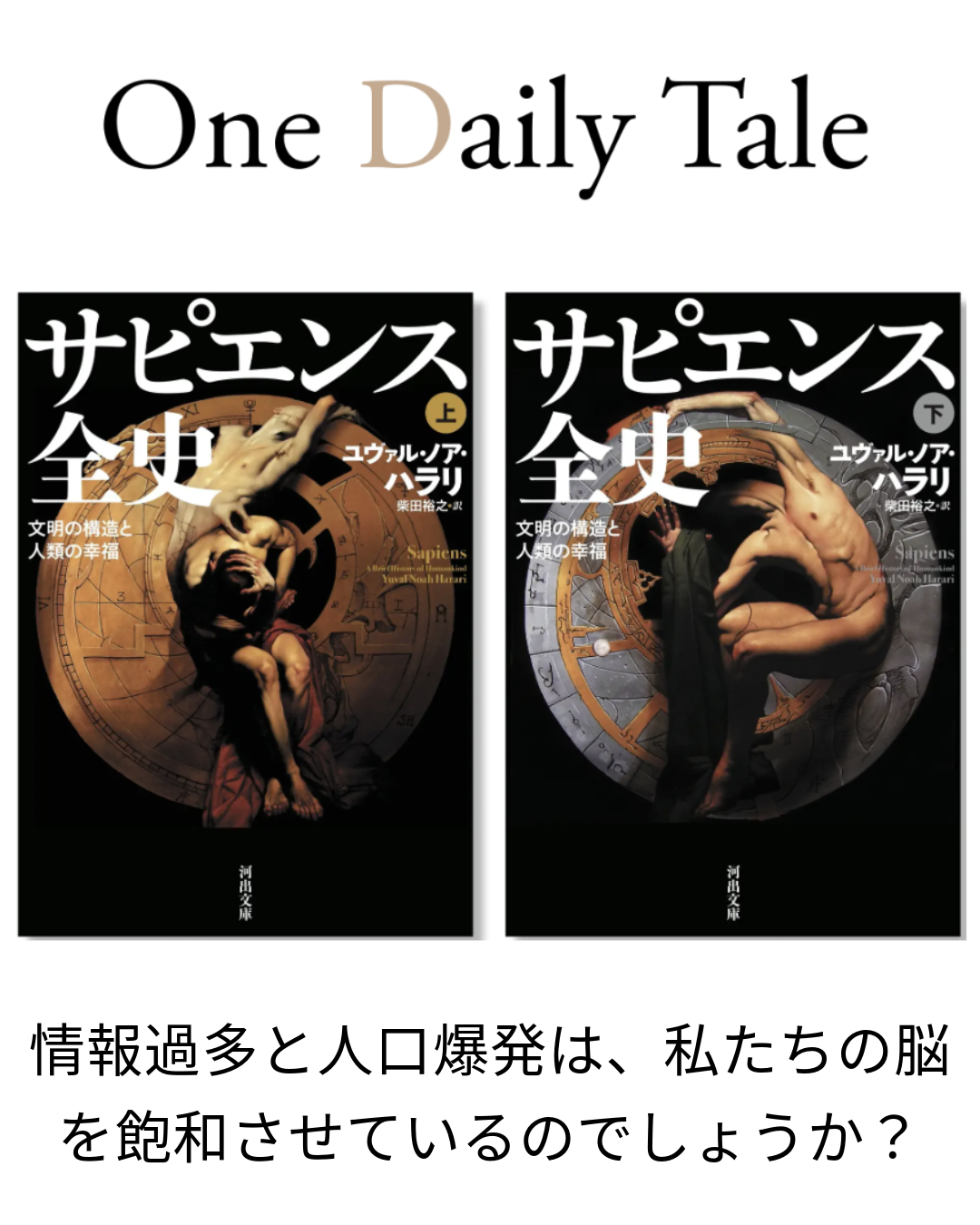
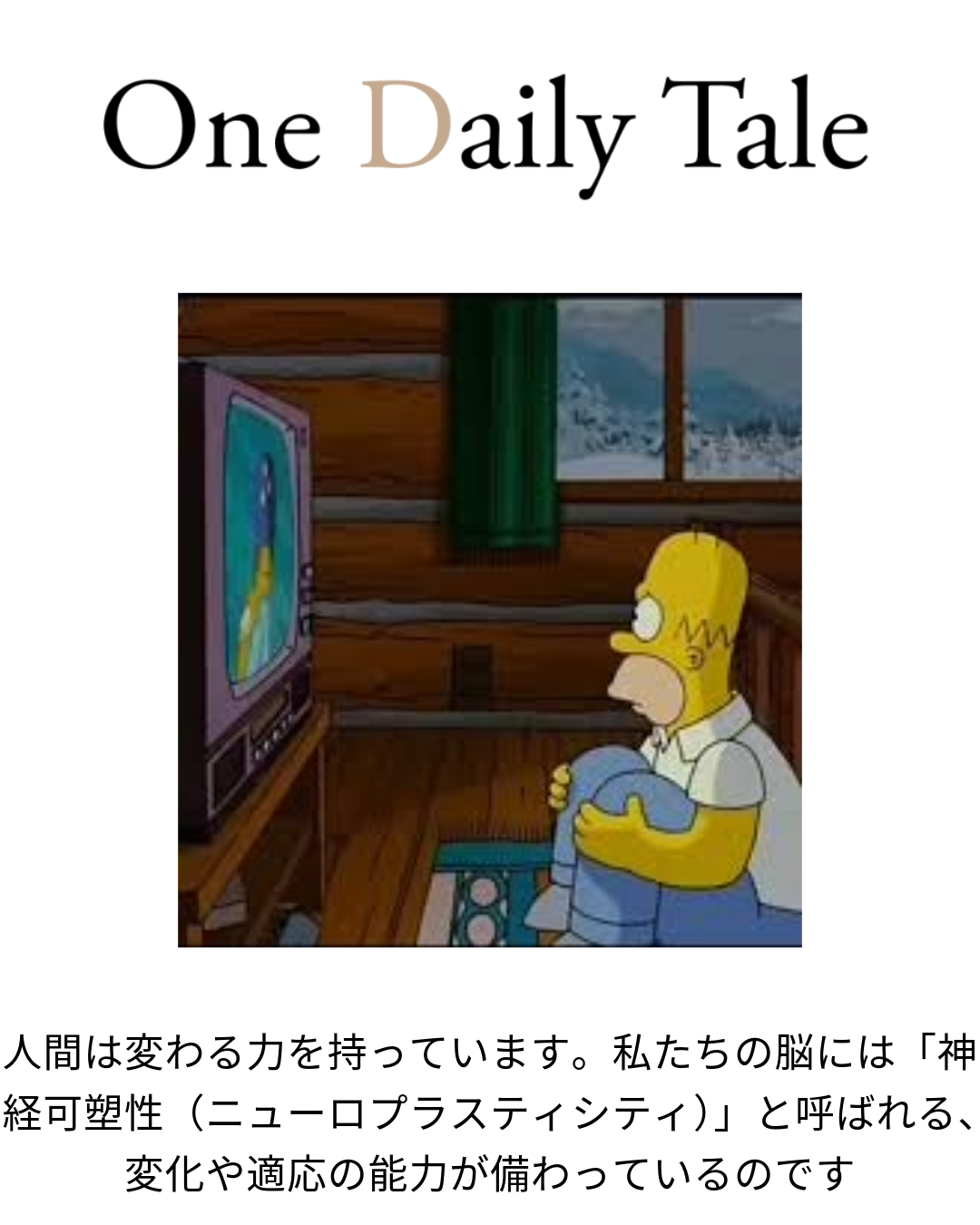

コメントを残す