数ヶ月前、妻と一緒にドラマ「Woman」を観ました。妻は主役を務める満島ひかりさんの大ファンで、大好きなこのドラマを私にも紹介したいと思ったのです。日本のドラマをご存じない方のために説明すると、ドラマは通常、1週間に1回放送される10~12話程度のミニシリーズです。テーマは幅広く、サスペンスやコメディなどがありますが、中でも最も人気があるのは間違いなく感動的で家族に焦点を当てた作品です。「Woman」はまさにそのジャンルに属します。正直なところ、これまで観たドラマの中には、ストーリーや演技の質がいまひとつで少し気恥ずかしいものもありましたが、この作品は質が高く、とても印象的でした。
最近、アンドリュー・フバーマン氏とアラン・ショア博士による「人間関係が脳に与える影響」というポッドキャストを聴いた後、このドラマについて改めて考え直しました。
小春の物語:脆さの中の強さ
「Woman」のストーリーは、一見すると少し現実離れしているかもしれませんが、この作品の魅力は間違いなく主人公小春と彼女の驚くべき成長にあります。悲劇的な事故で夫を失った後、小春は幼い二人の子供を一人で育てることを余儀なくされます。さらに、自身が病気であることが判明し、子供たちの幸福を第一に考えるため、20年以上疎遠だった母親と再び関わる決断をします。母親は再婚し、別の娘もいます。
この再会がドラマの中心テーマである「手放すこと」を象徴しています。ショア博士は、癒しと脳の右半球の修復には、手放すことや脆さを受け入れることがいかに重要であるかを説明しています。母親と話す決断をすることで、小春はこの癒しのプロセスを開始します。過去を完全に許したり忘れたりすることはできなくても、手放すことで新たな一歩を踏み出すことができます。
ドラマが示しているように、真の強さとは、脆さを認め、自分の感情に正直であることにあります。これらの特性は社会では弱さと見なされることが多いですが、このパラドックスを誰もが抱えています。小春の成長は貴重な教訓を与えてくれます。感情を受け入れることで、自己認識を高め、前進することが可能になります。彼女は物語の中で二度この変化を示します。一度目は母親に対して、二度目は妹に対してです。どちらの場合も、小春の心の変化が大きな影響を与え、感情的な結び目を解き、和解への道を開きます。
幼少期の感情発達の重要性
ドラマのもう一つの重要なテーマは、ショア博士が語る新生児期、さらには胎児期の感情発達の重要性に響きます。この期間、主要な養育者、多くの場合母親は、赤ちゃんの感情を直感的なレベルで調整する重要な役割を果たします。
赤ちゃんの右脳は感情処理を担い、左脳(論理や認知を司る)は3歳頃から発達します。そのため、養育者が赤ちゃんと右脳同士でつながる能力が非常に重要です。ドラマの中で小春は、どんな困難にもかかわらず、子供たちの安全と感情的な幸福を最優先に考えています。
この行動は、ある重要な真実を強調しています。子供たちの可能性を引き出すには、まず自分自身を整える必要があります。親の感情的な健康は、安定した愛情を提供する能力に直接影響します。「Woman」は、小春が自身の試練に立ち向かい、子供たちに最高のものを与えようとする姿を通じて、このテーマを美しく描き出しています。
脆さと強さの関係、または幼少期の経験が感情に与える影響についてどう思いますか? コメント欄でぜひご意見をお聞かせください!

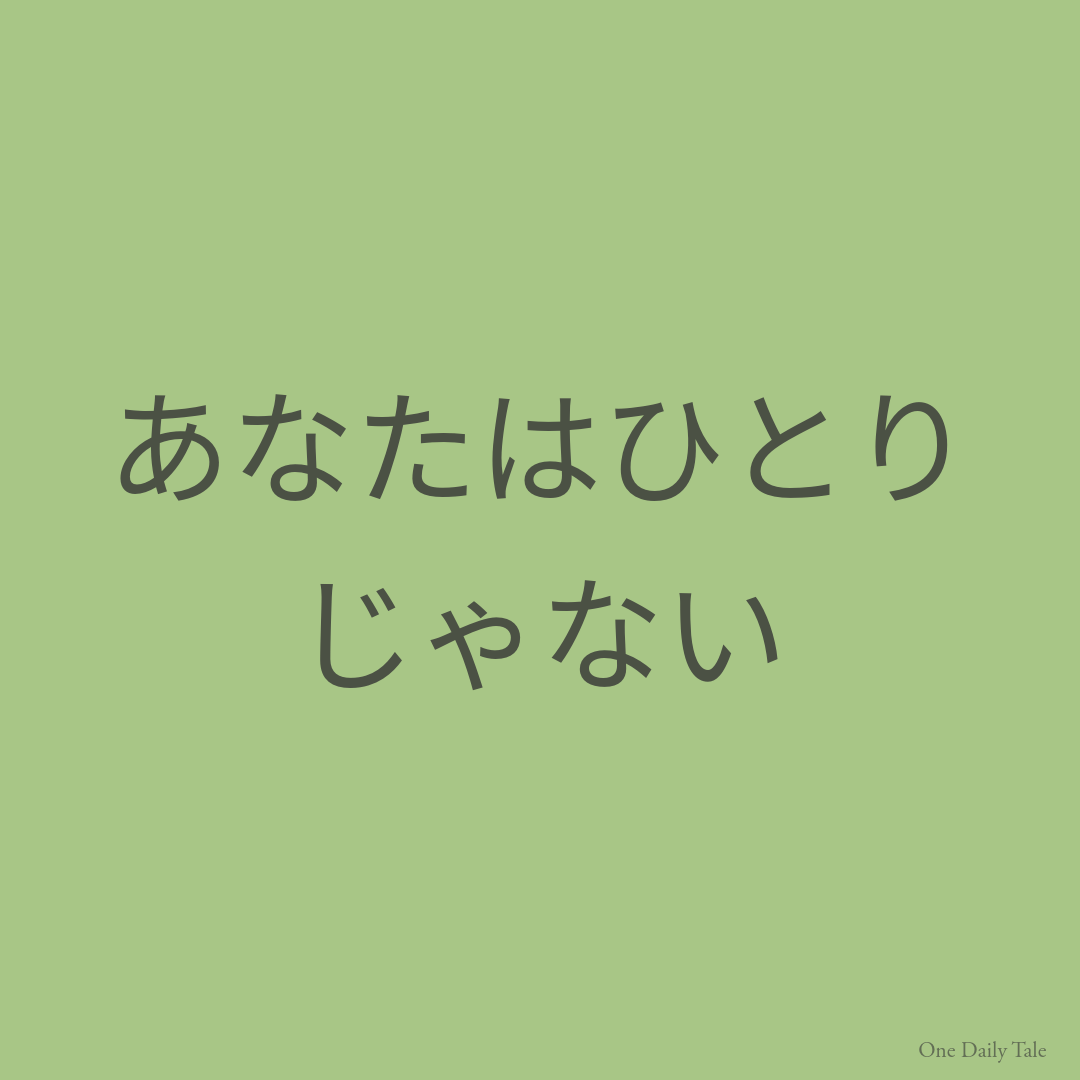
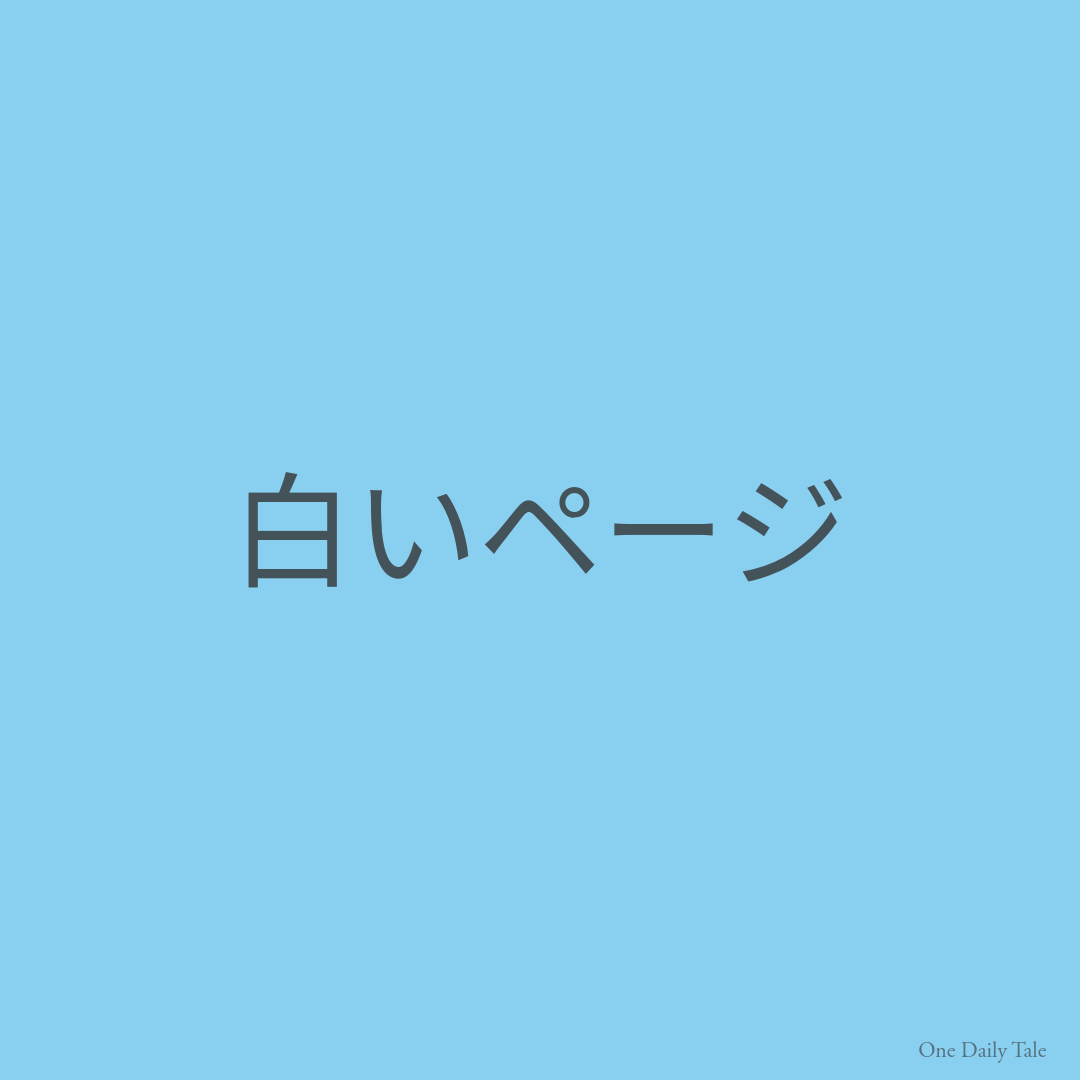

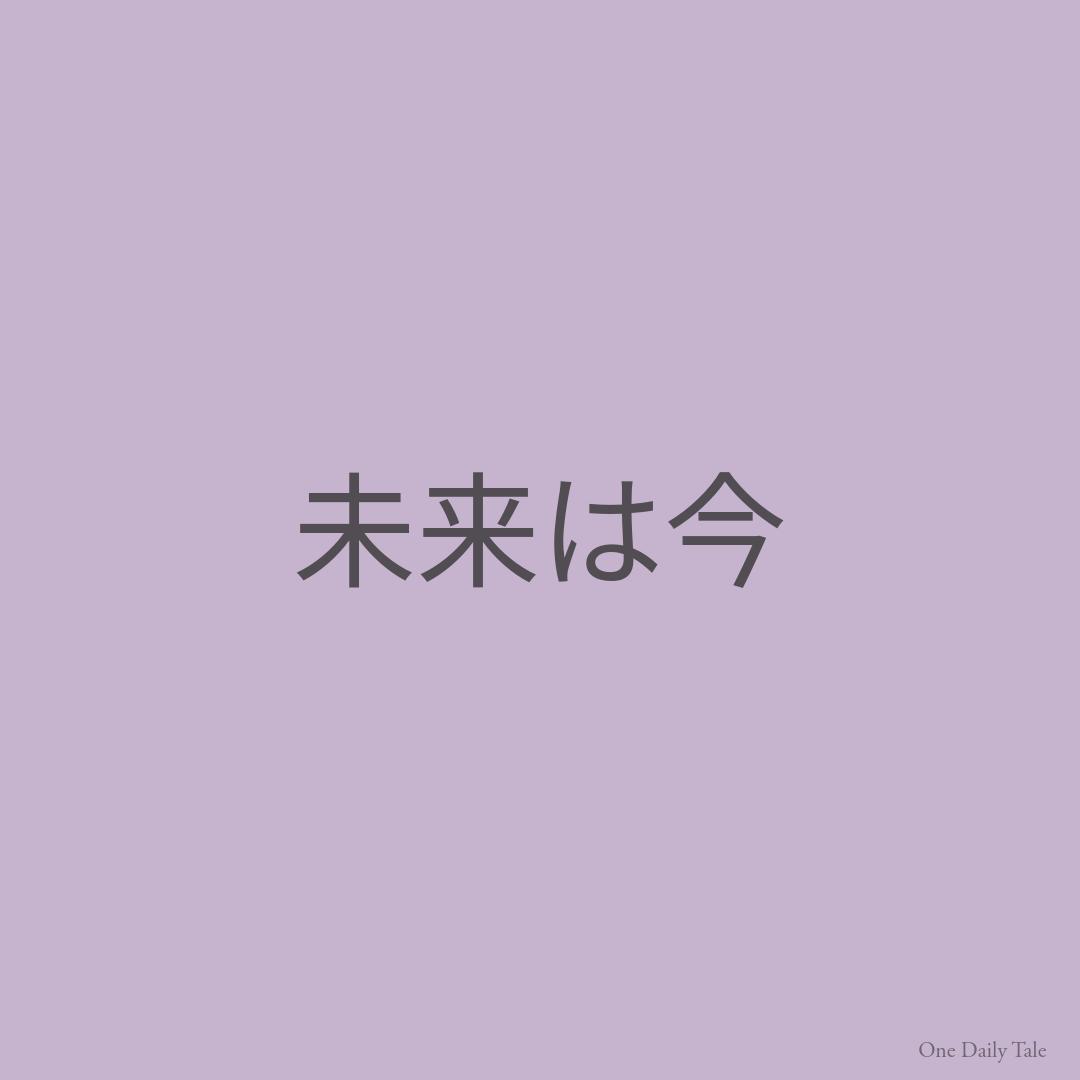
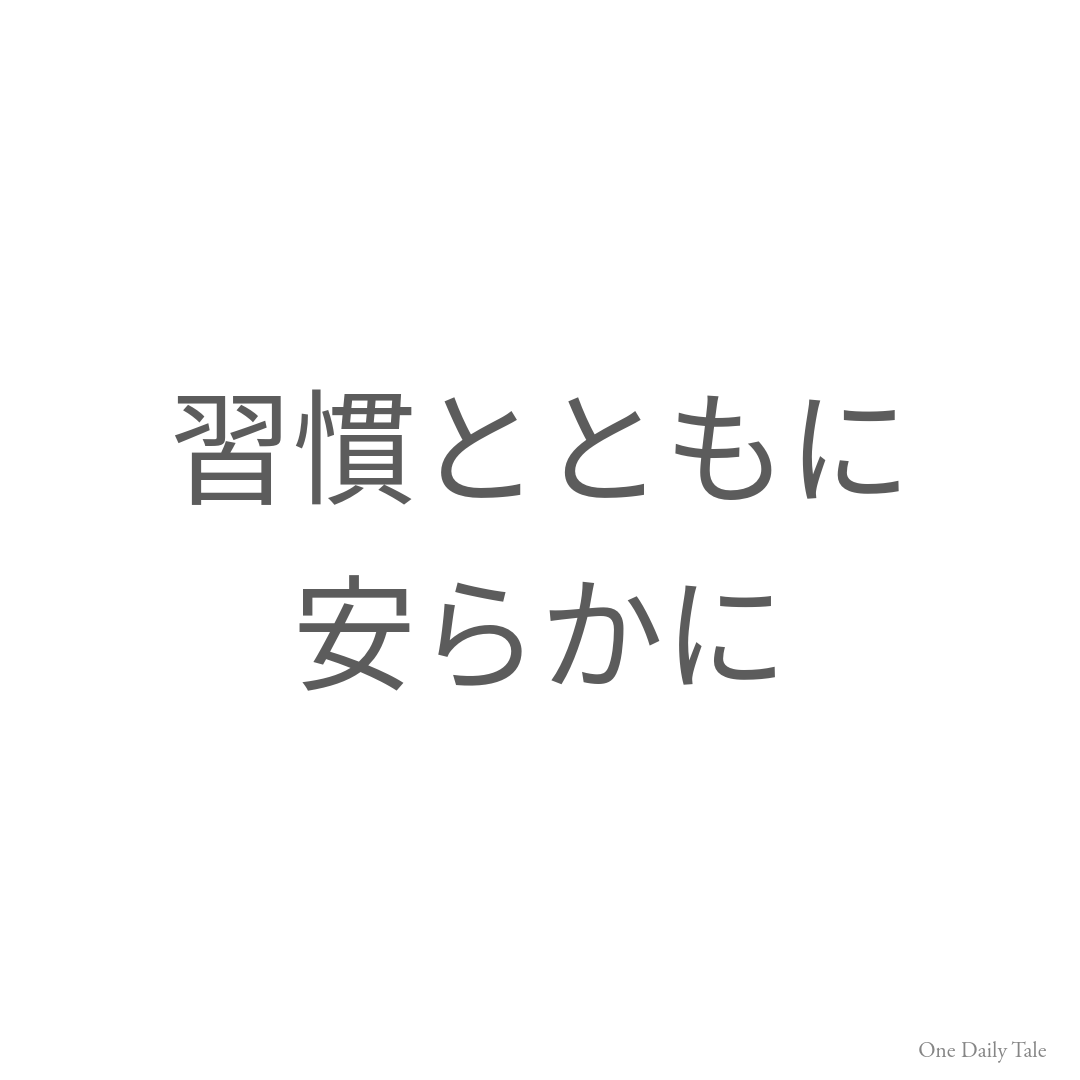
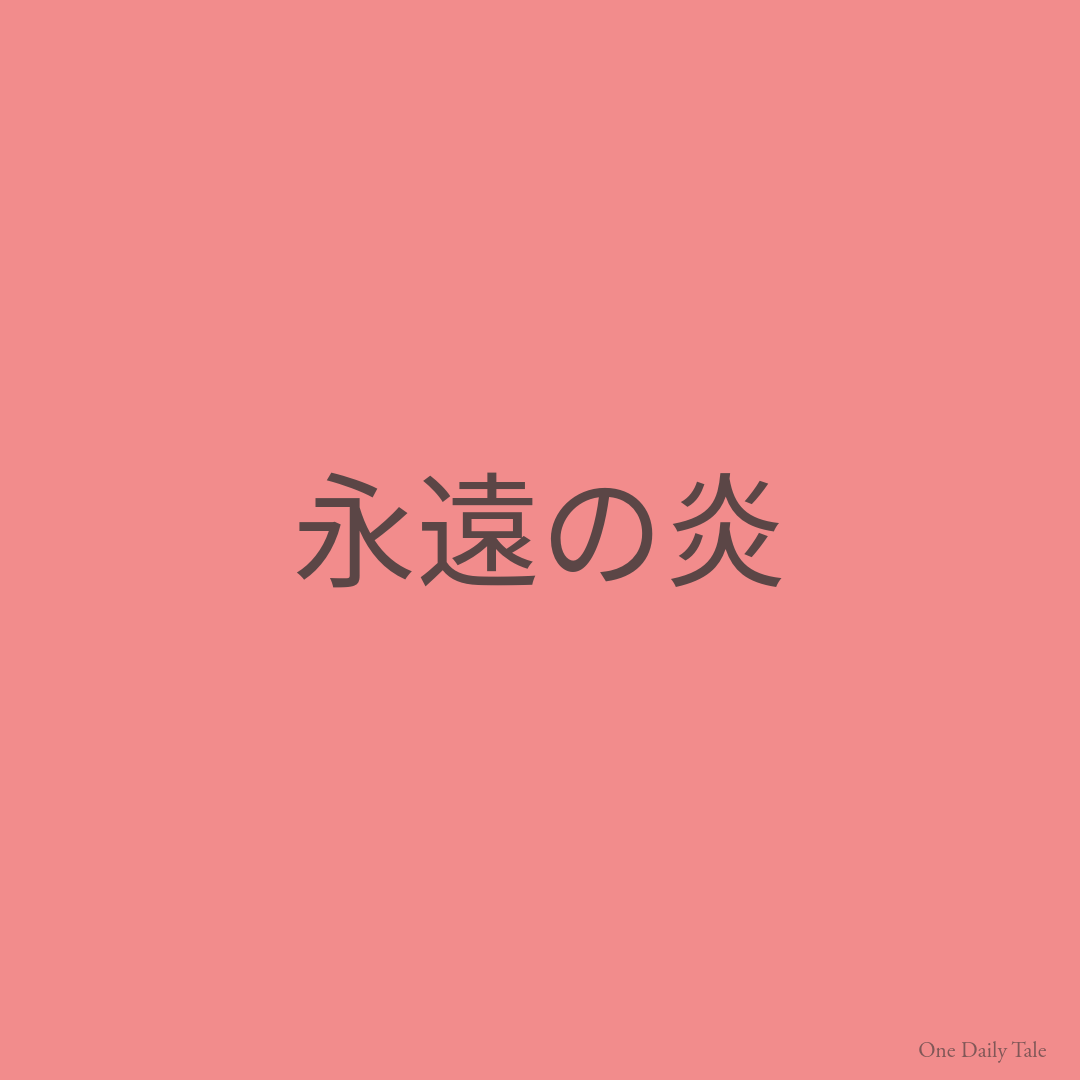
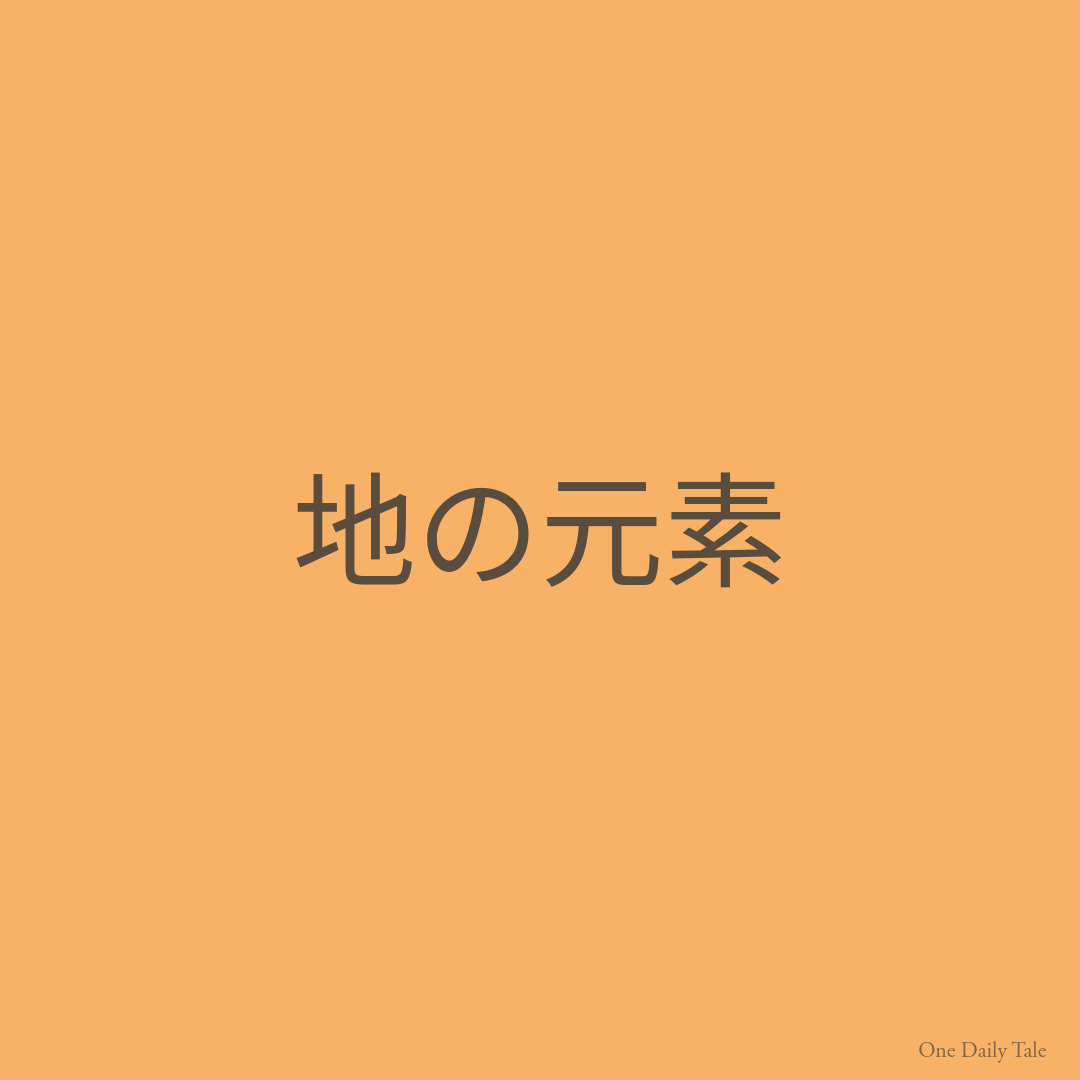
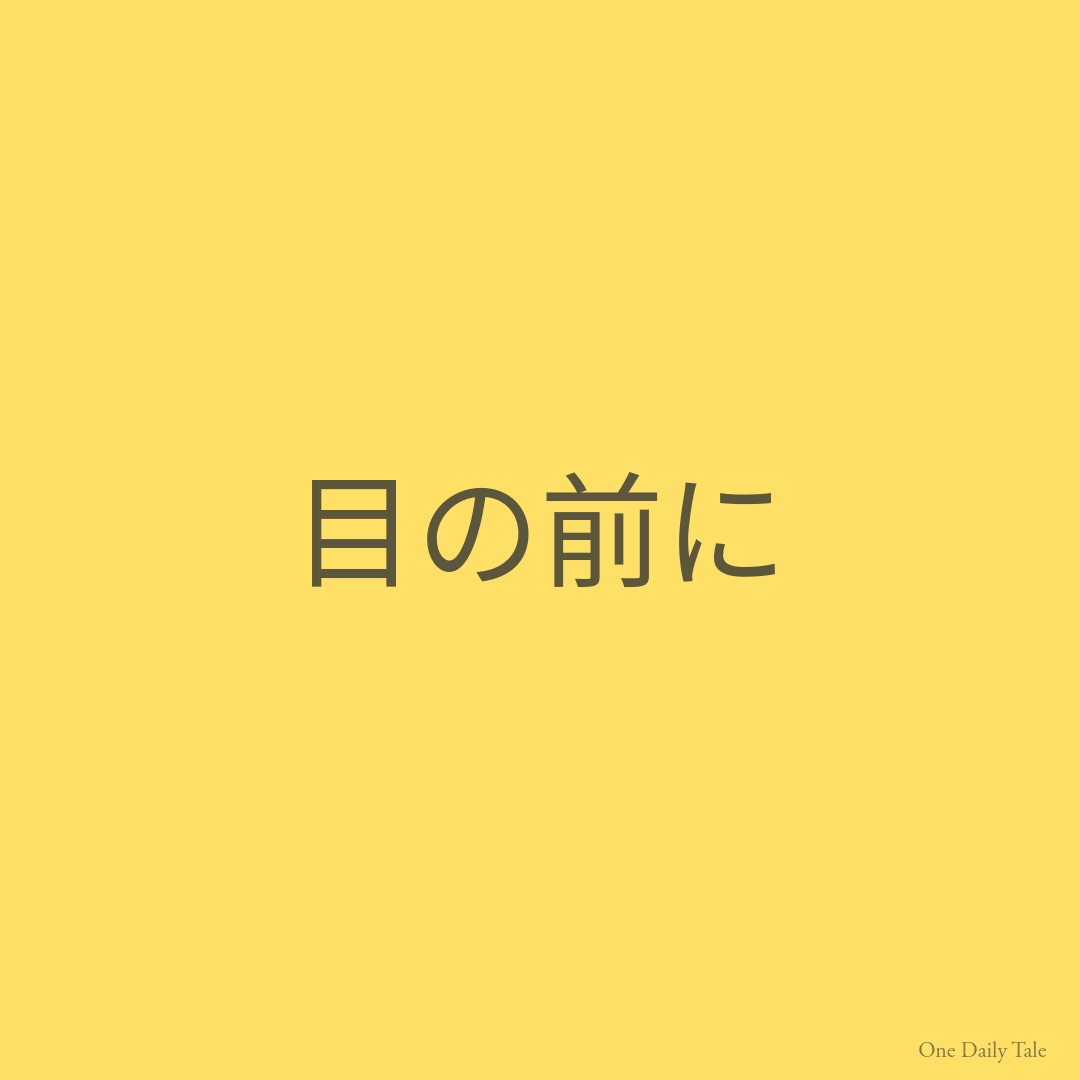
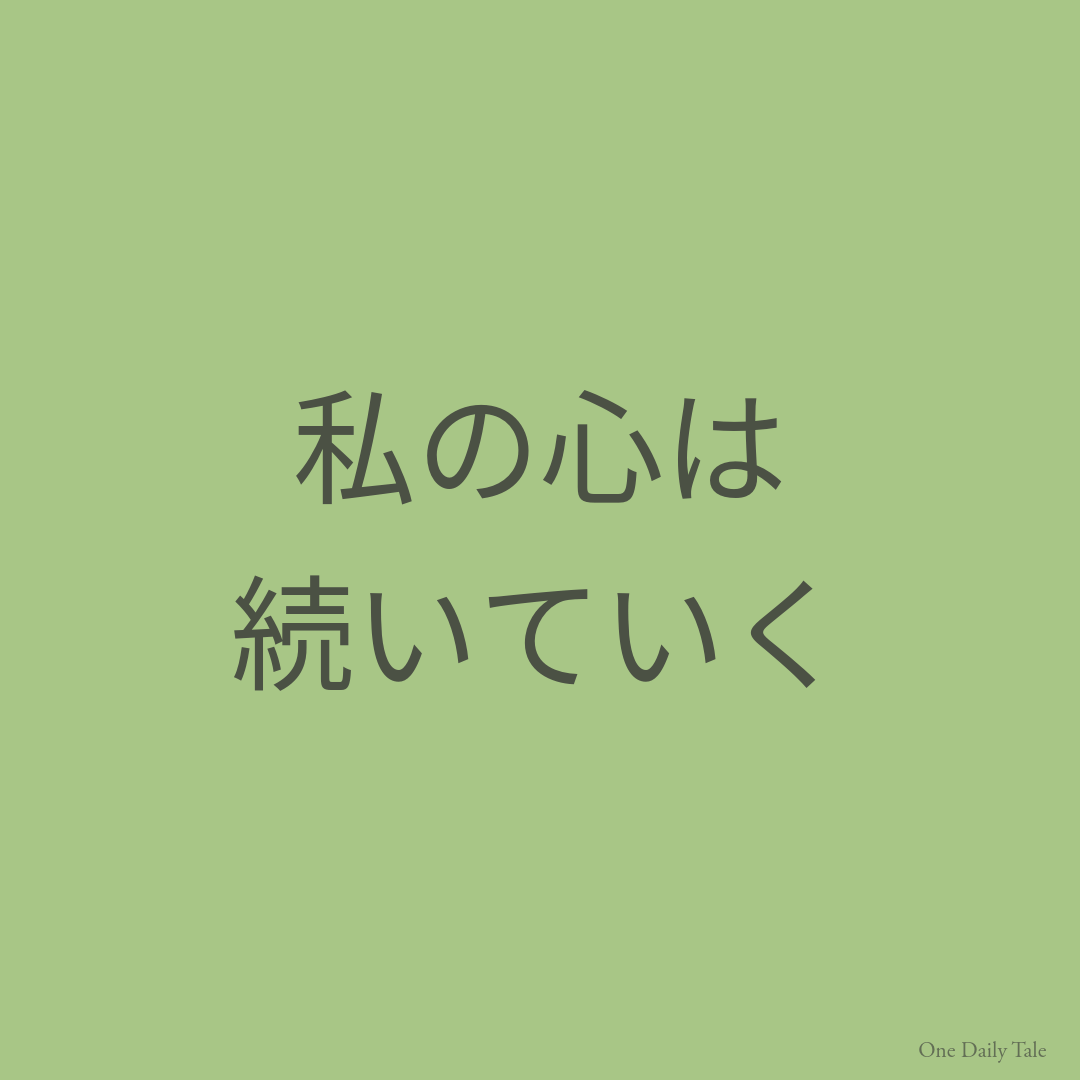
コメントを残す