オーディションは、1999年に公開された三池崇史監督の日本のホラー映画です。私はフランスに住んでいた頃、テレビチャンネルArteで初めて観ました。三池監督はその衝撃的な作品で知られていますが、この映画は村上龍の小説を原作とした傑作です。物語は、中年の未亡人が映画プロデューサーの友人と共に恋人探しのために偽のオーディションを企画するところから始まります。しかし、彼が選んだ浅見は、暗い過去を抱えており、それが彼らの関係に大きな影響を与えます。
この映画は、フェミニズム的でもあり、ミソジニー的でもあると批判され、また称賛されています。この興味深い矛盾は、さらなる考察を促します。
「オーディション」におけるフェミニズムとミソジニー
物語のミソジニー的な側面は、オーディション自体にあります。それは、美の基準に固執する社会を完璧に象徴しています。これは特に日本やアジアにおいて顕著で、アイドル文化がいまだに根強い人気を持っています。身体的な側面やその他の基準を問わず、私たちの社会は人々を型にはめようとし、そこに当てはまらない人々は排除されがちです。
一方で、浅見が加害者に復讐する部分は、フェミニズム的な側面と見なされています。この映画が公開された時点では#MeToo運動は存在していませんでしたが、現在では女性が声を上げ、平等と正義を求める社会の変化が徐々に見られるようになりました。この映画は、不平等がジェンダーに限らず、人間の基本的なニーズへのアクセスにも及ぶ、社会の根本的な欠陥であることを強調しています。
浅見の心理とその広範な影響
浅見の幼少期の虐待に彩られた過去は、彼女の行動の心理的な背景となっています。彼女の物語は、幼少期の経験がいかにして精神的健康を形作るかを示しています。人間の脳は約25歳まで発達し続け、その後も神経可塑性のおかげで適応する能力を持ち続けます。
つまり、親や養育者の役割は、子どもの精神的な健康にとって極めて重要です。子どもの感情に耳を傾け、判断せずに受け止め、そのエネルギーを調整し、安全な環境を提供することが求められます。しかし、多くの大人はそのために必要な自己調整能力を欠いているのが現実です。社会や養育者が良い手本を示せなければ、子どもたちはどのようにして必要なスキルを身に付けることができるでしょうか?
次世代のための社会の再構築
One Daily Taleでは、特に子どもたちのために、人類の幸福を最優先に考える社会を提唱しています。現在の社会構造は、不平等に満ちており、子どもや大人が繁栄するために必要な支援体制を提供できていません。この基本的なニーズに応えるために社会を再構築することが、より良い未来を築く鍵であると私たちは主張します。
皆さんはどう思いますか?
オーディションは、フェミニズムとミソジニーの要素をうまくバランスさせていますか、それともどちらか一方の視点が物語を支配していると思いますか?また、社会はどのようにして子どもや大人に影響を与える不平等を改善できるでしょうか?ぜひコメントでご意見をお聞かせください!

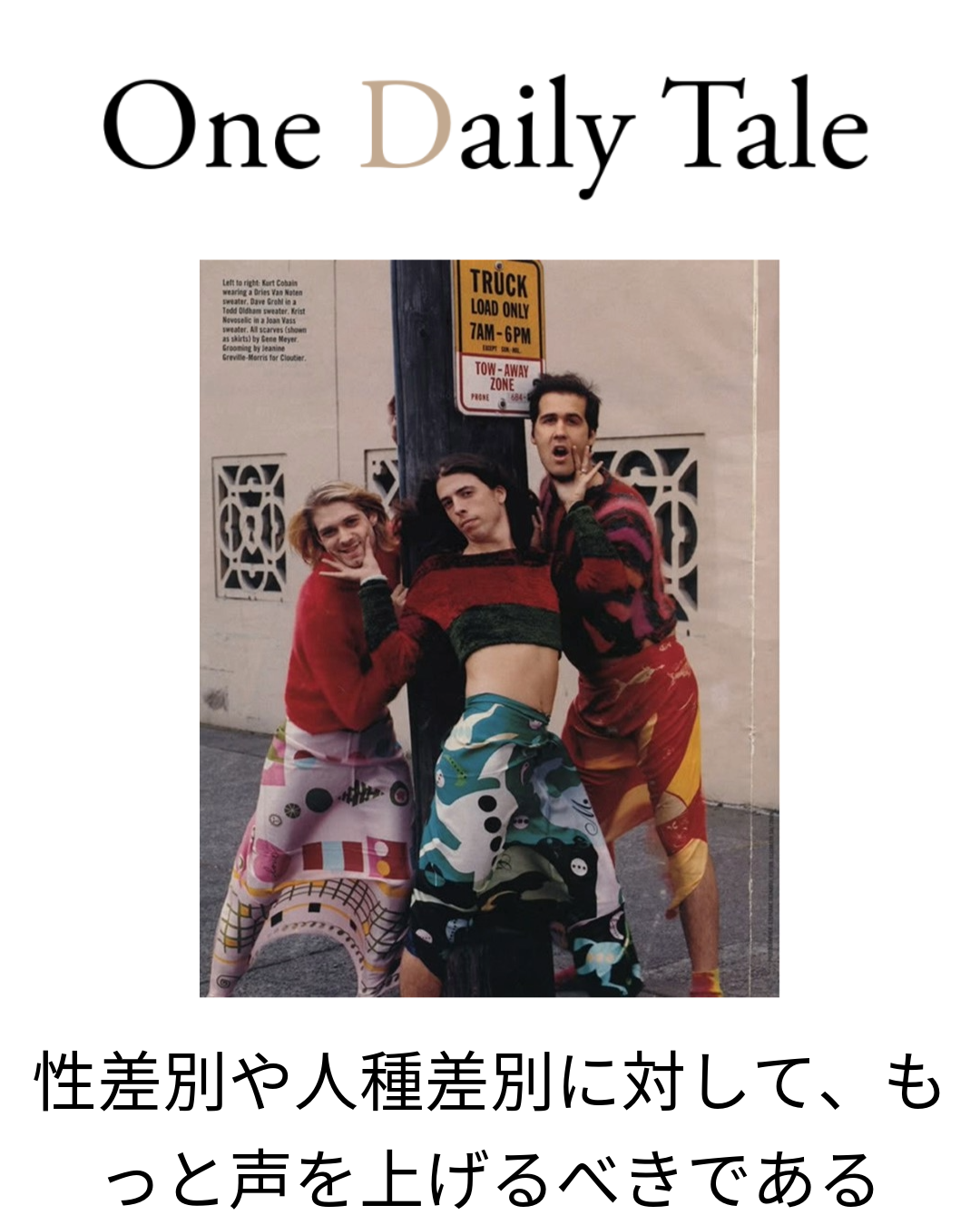
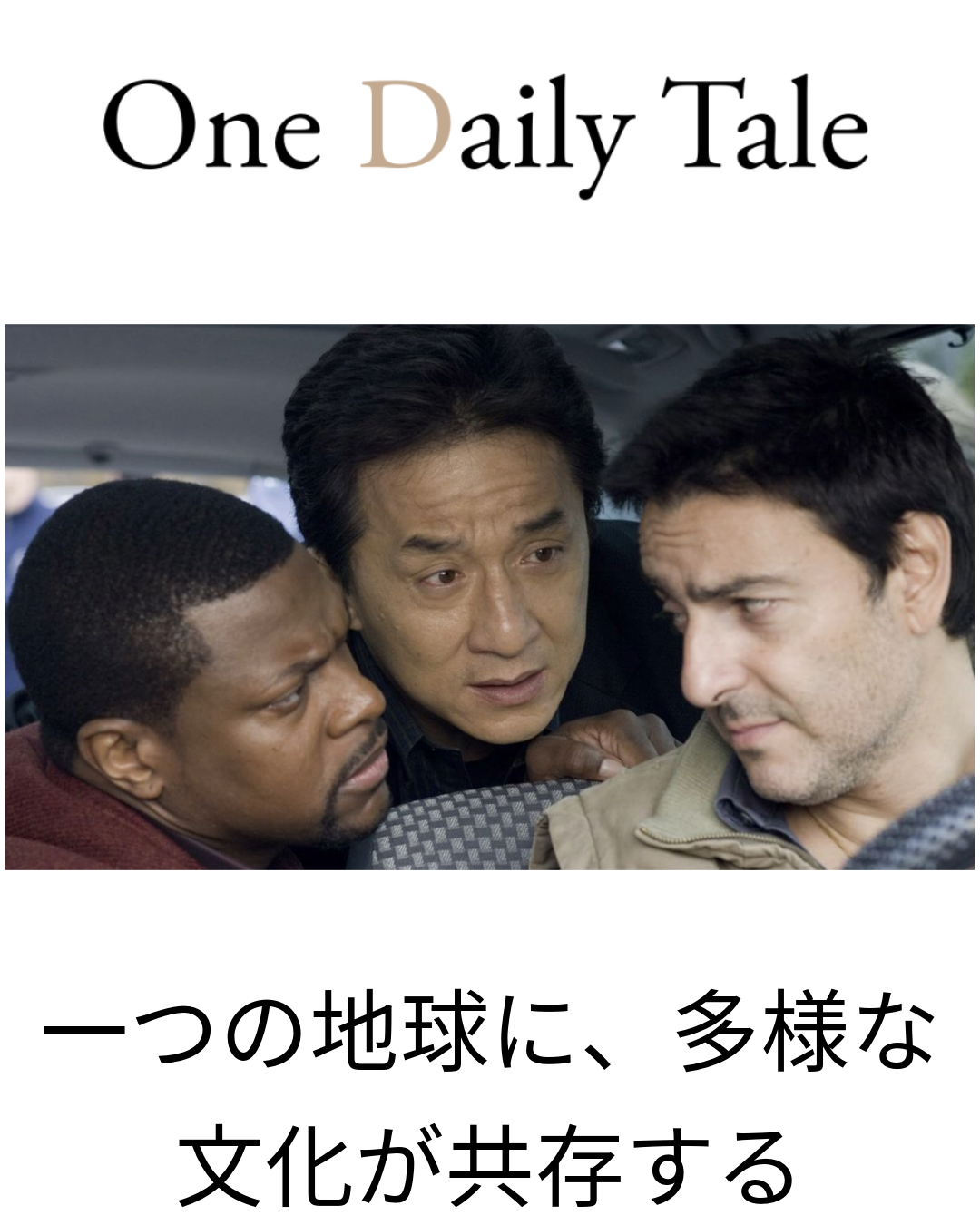




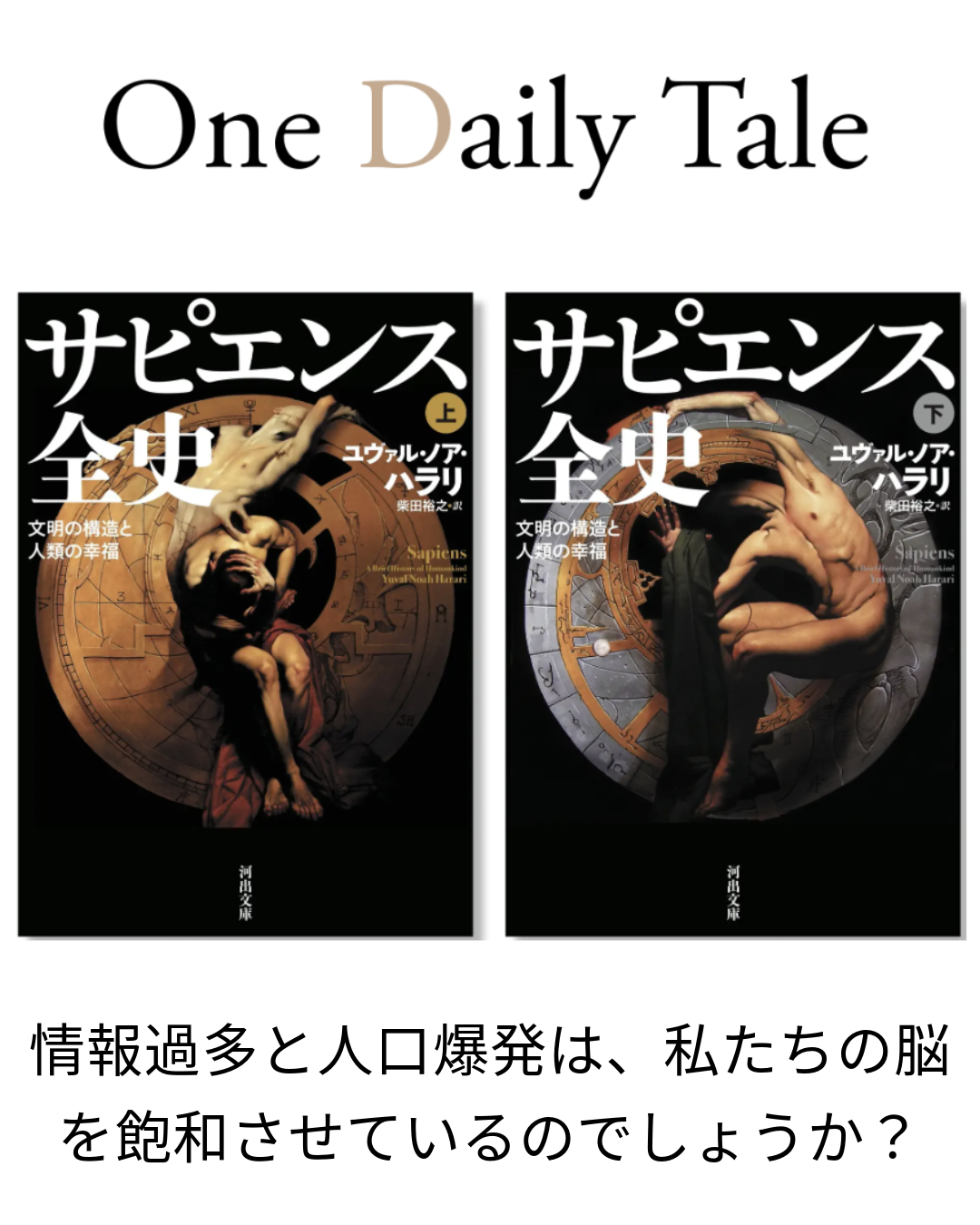
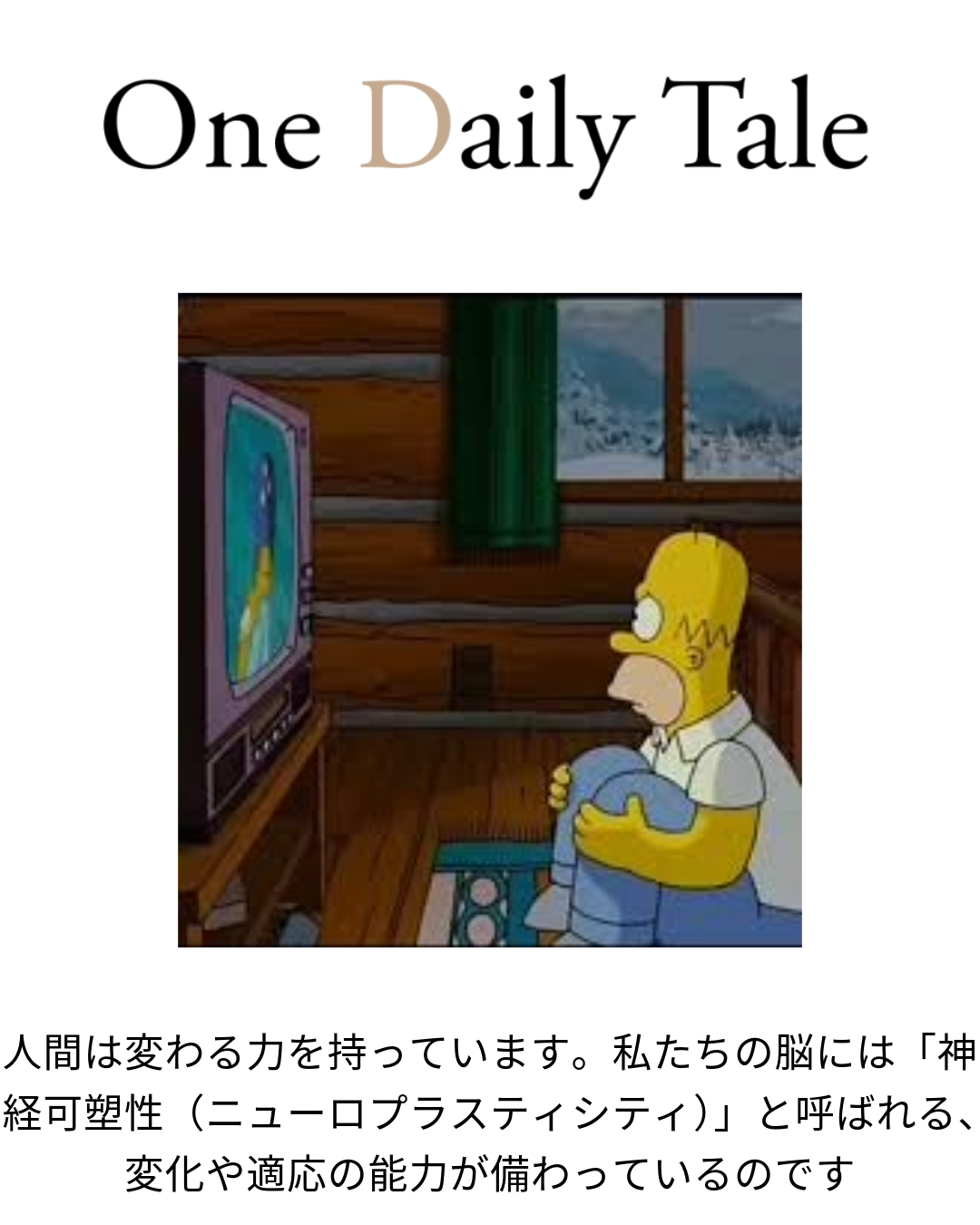

コメントを残す